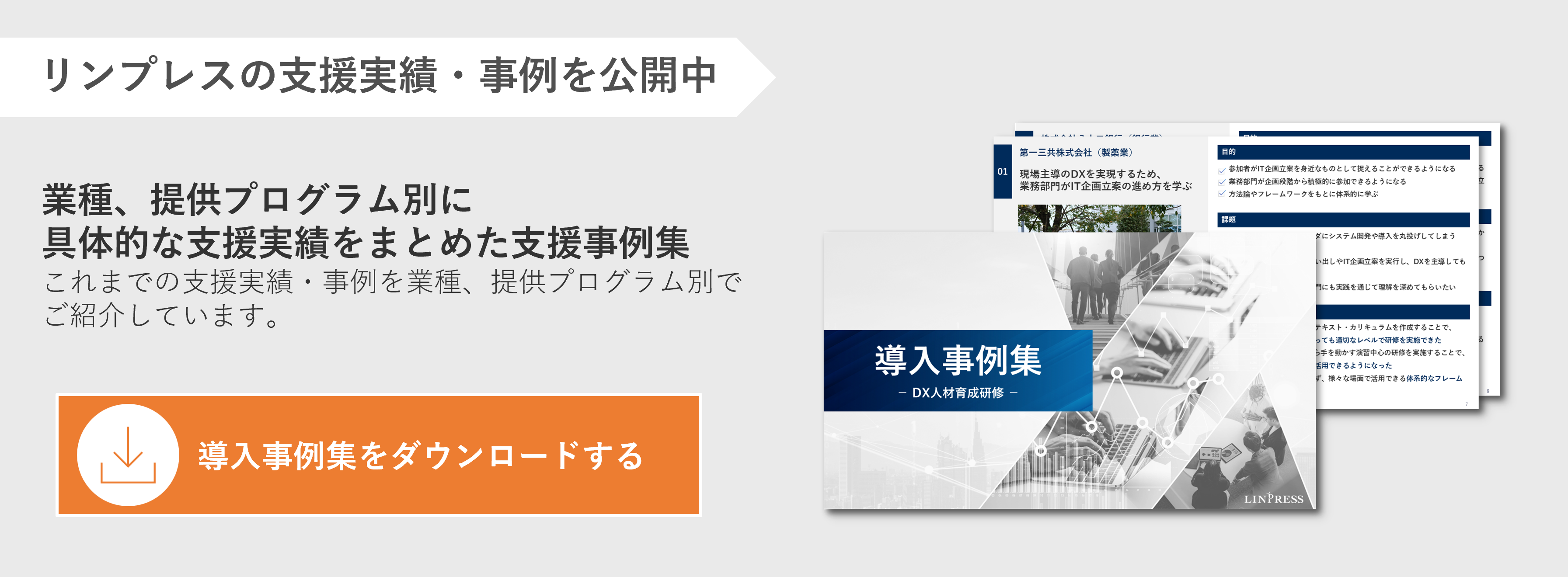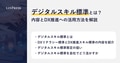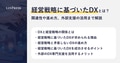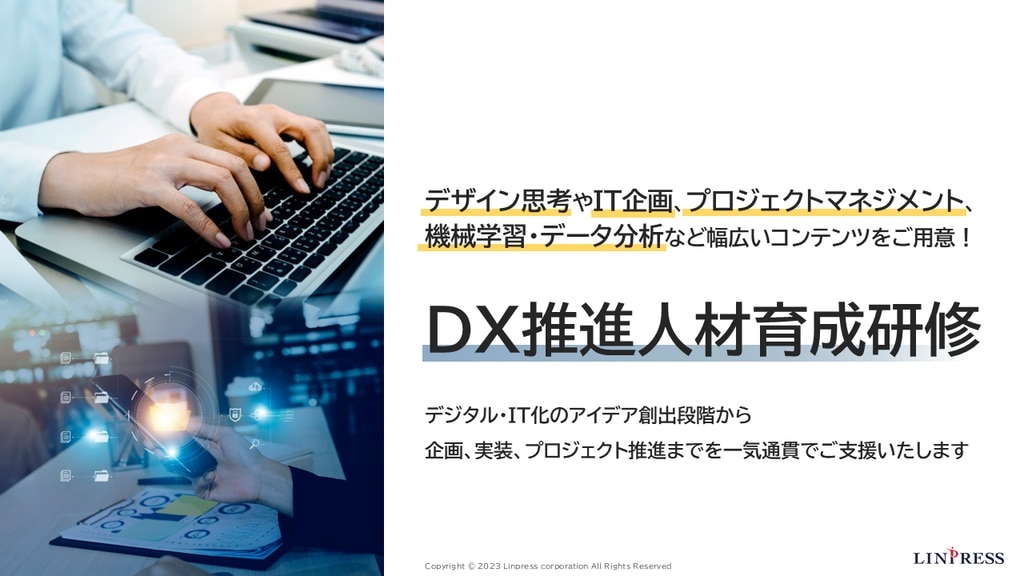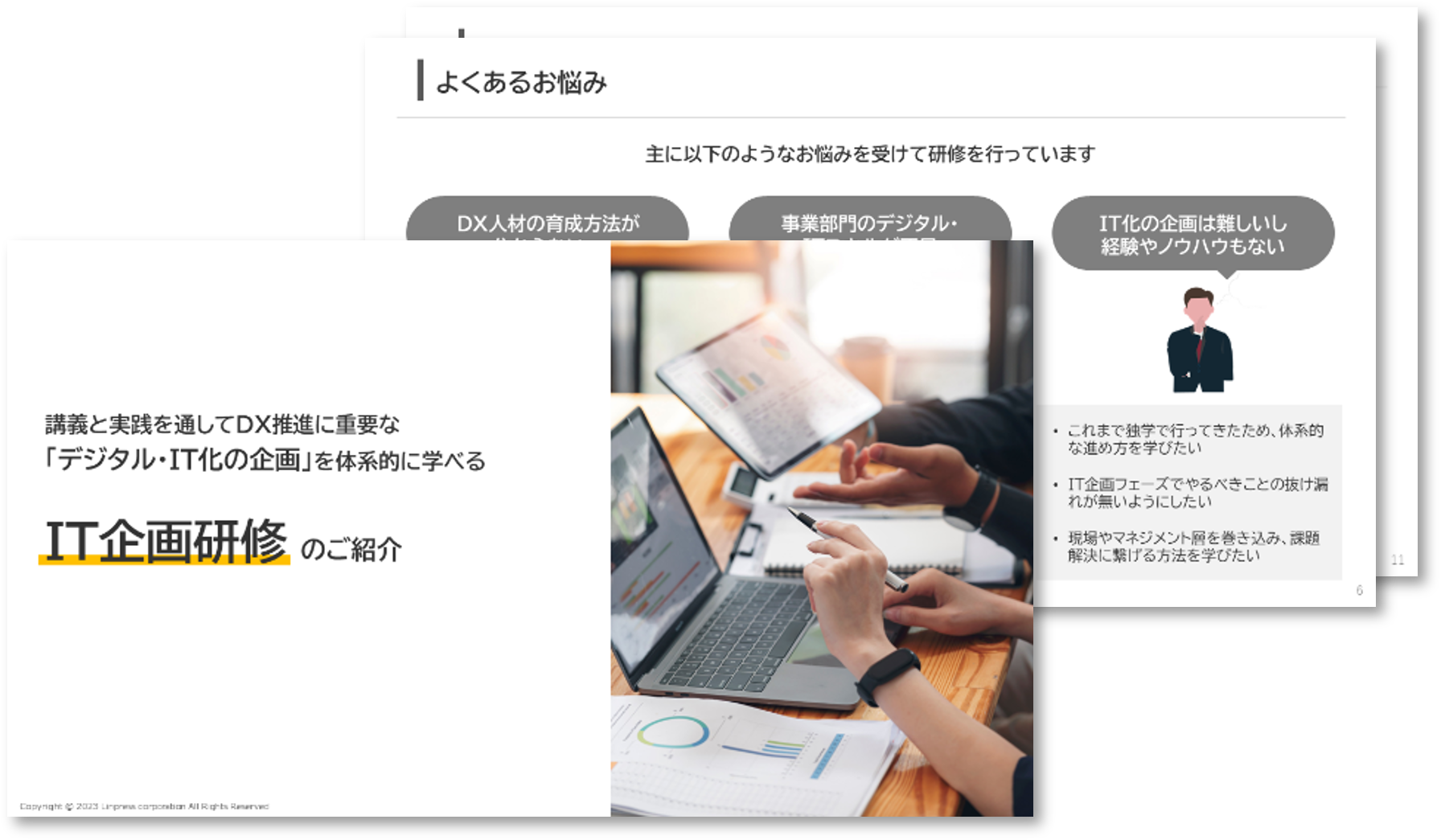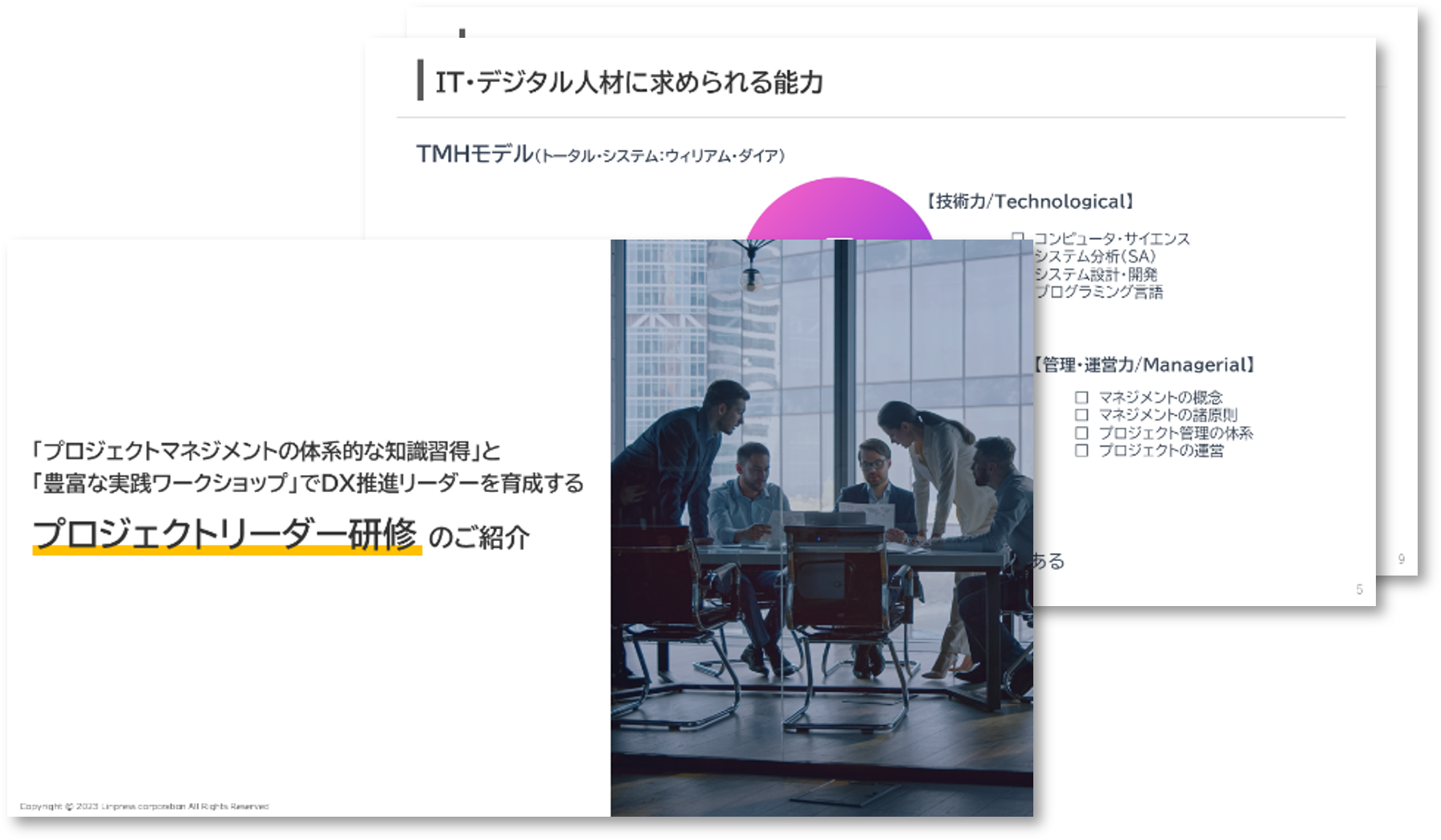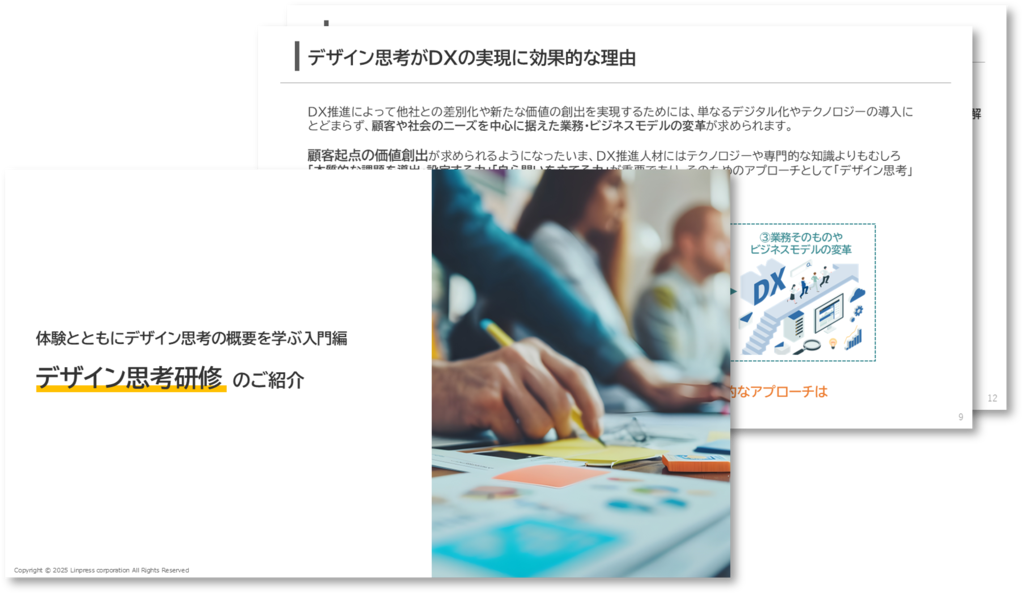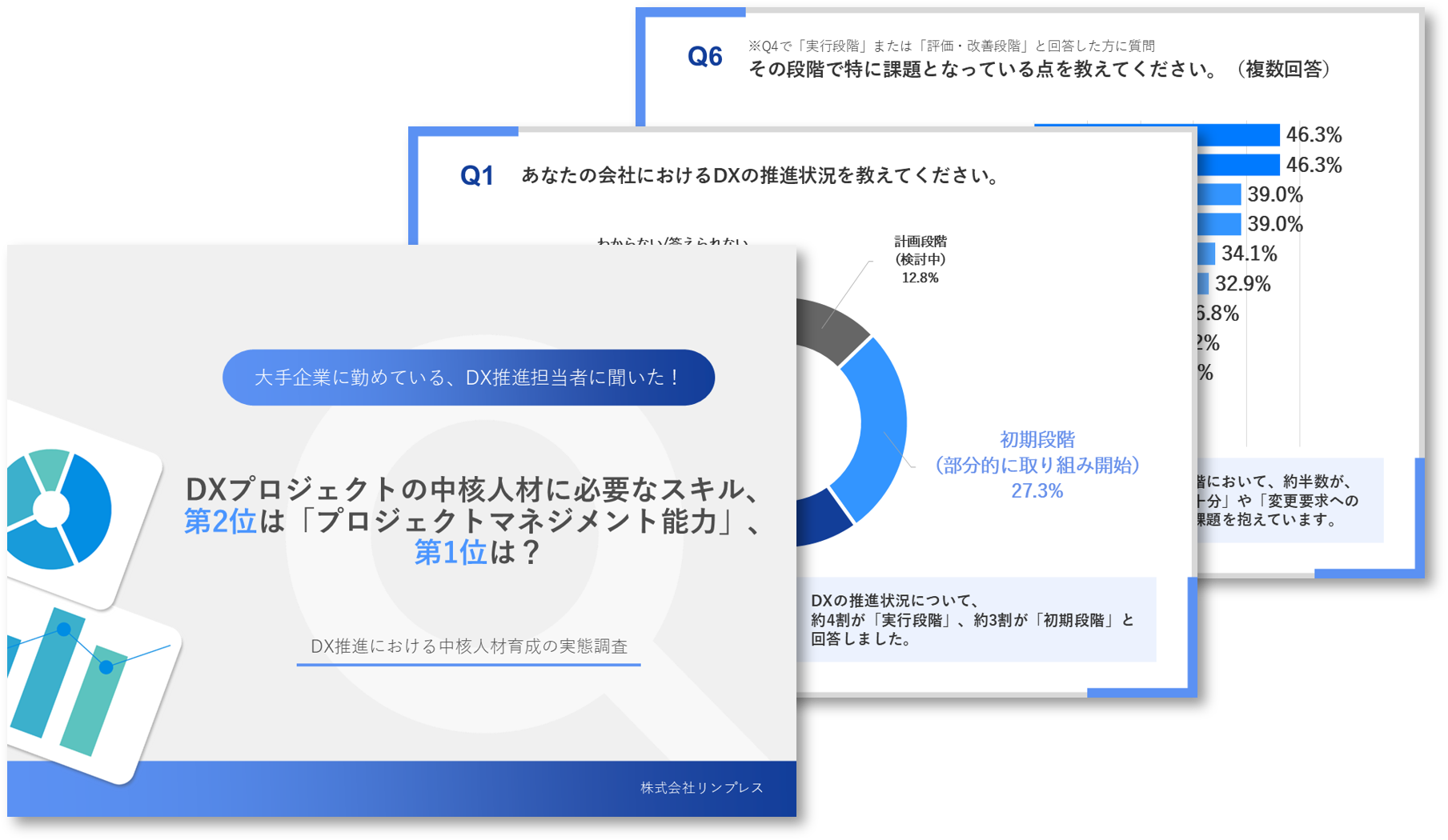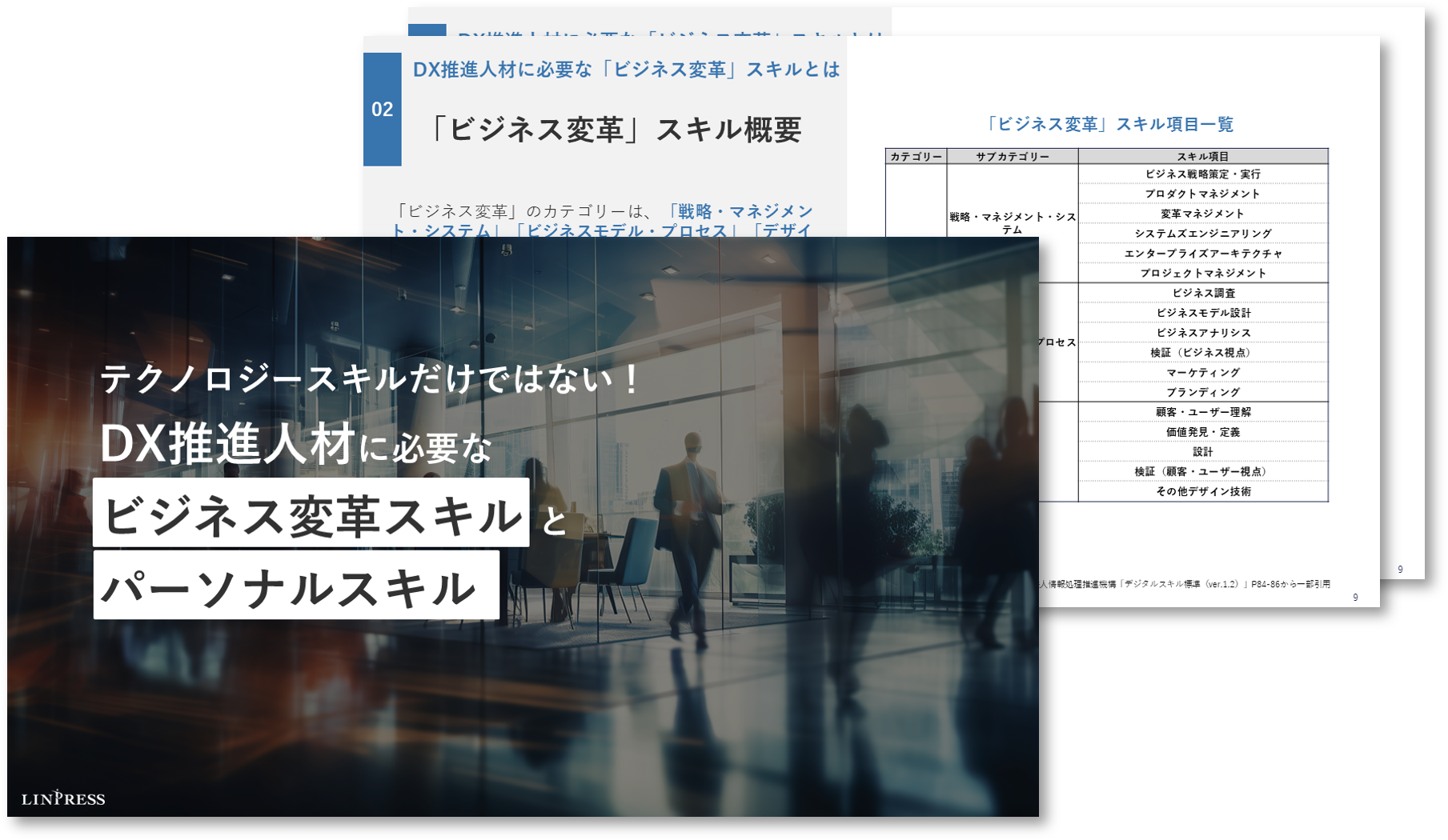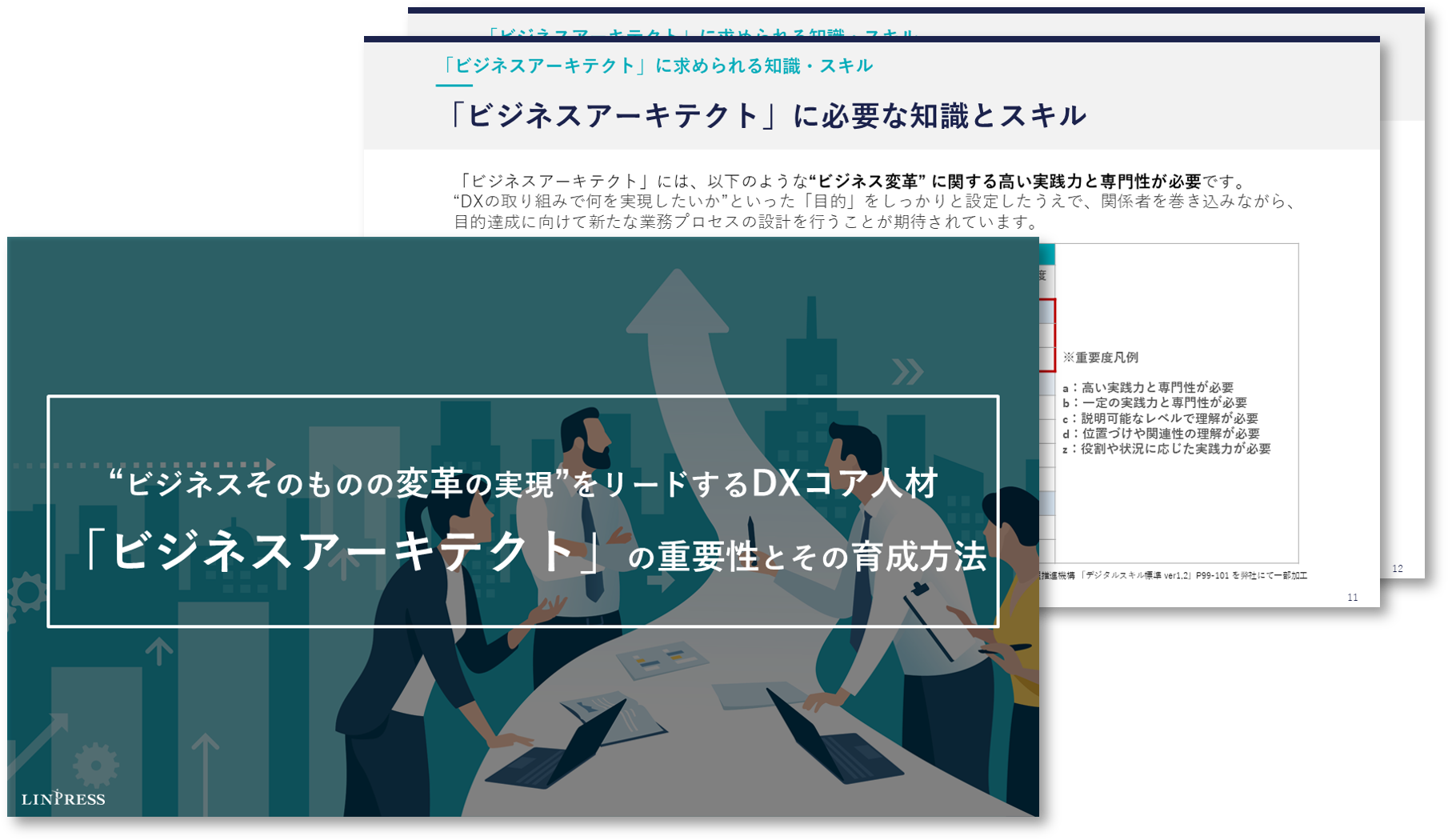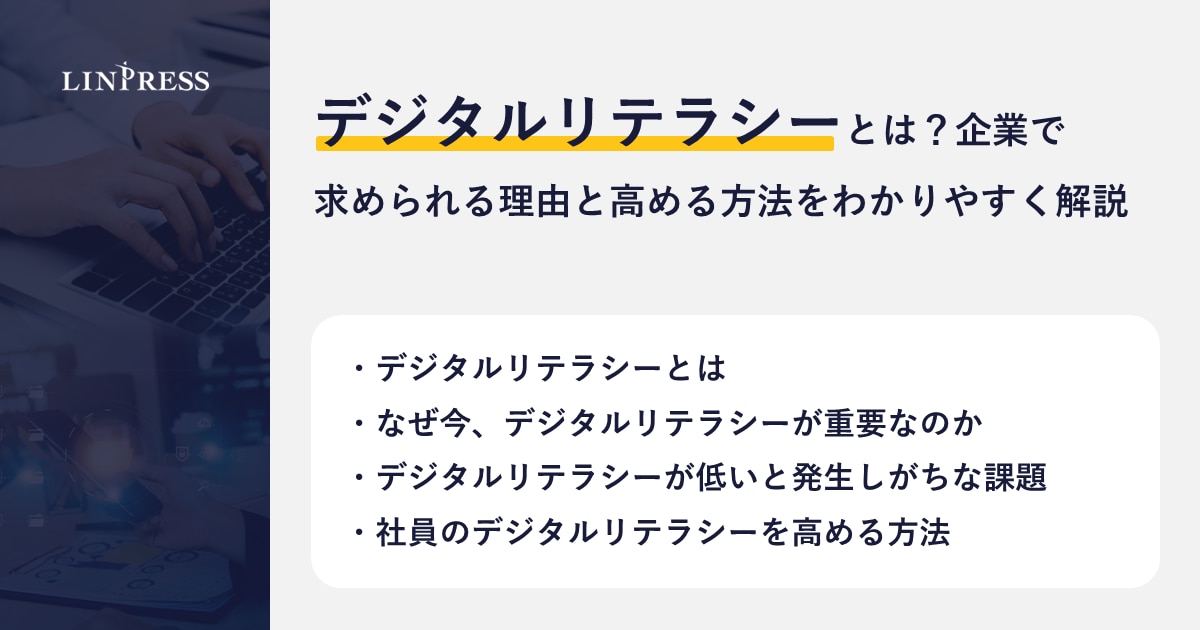
デジタルリテラシーとは?企業で求められる理由と高める方法をわかりやすく解説
ビジネスのデジタル化が加速する現代において、すべての社員に求められているのが「デジタルリテラシー」です。これは単なるITスキルではなく、ツールやシステムを正しく理解し、活用するための「ビジネス基盤力」ともいえる重要な素養です。
本記事では、デジタルリテラシーの定義や企業にとっての必要性を解説するとともに、社員のデジタルリテラシーを高めるための具体的な方法をご紹介します。
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
デジタルリテラシーとは?
デジタルリテラシーとは、パソコンやインターネット、各種ソフトウェア、デジタル機器などを使いこなし、情報を的確に収集・判断・活用できる力を指します。単にITツールを操作できるというだけではなく、業務や社会生活の中でデジタル技術を適切に使いこなす判断力や活用力まで含まれるのが特徴です。
急速なデジタル化が進む現代において、すべてのビジネスパーソンに求められる基礎的な素養となっており、業種や職種を問わず必要とされています。
経済産業省やIPAによる定義・枠組み
経済産業省とIPA(情報処理推進機構)は、デジタルリテラシーの重要性を明確にするために「デジタルスキル標準(DSS)」を策定し、その中で「DXリテラシー標準(DSS-L)」を提示しています。
このDSS-Lでは、すべてのビジネスパーソンが共通して身につけるべきリテラシーとして以下の4領域が定義されています。
Why:なぜDXが必要かという背景理解
What:どのような技術やデータが使われるか
How:技術・データをどう業務に活かすか
マインド・スタンス:変化に柔軟に対応する姿勢
これらは役職や担当業務を問わず、全社員に求められる「DXの基礎体力」とも言えるスキル群であり、企業全体のDX推進力を底上げする上で不可欠です。
経済産業省が策定したリテラシーの指標については、以下の記事で詳しく紹介しています。
DXリテラシー標準の内容をわかりやすく解説|推進に役立つ活用ポイントとは
デジタルリテラシーが高い・低いの具体例
一般的に「デジタルリテラシーが高い人」「デジタルリテラシーが低い人」という評価を耳にすることも多いでしょう。しかし、実際にデジタルリテラシーが高い・低いとはどのようなスキルレベルを指すのでしょうか。それぞれの具体例を以下にまとめました。
デジタルリテラシーが高い例
業務効率化のためにExcelの関数やマクロを使いこなしている
社内ツールやクラウドサービスを使ってチームで円滑に情報共有できる
セキュリティ意識が高く、不審なメールやリンクを即座に見分けられる
ChatGPTなど生成AIの活用に前向きで、業務で使う際のリスクにも理解がある
デジタルリテラシーが低い例
メール添付やファイル名のルールを守れず、社内業務に支障をきたす
オンライン会議ツールの基本操作が分からず、業務に遅れが出る
セキュリティ対策の重要性を理解せず、パスワードを他人と共有する
新しいツールの導入に抵抗感が強く、学ぼうとする姿勢がない
このように、単なるツールの使い方だけではなく、「デジタル環境に適応する姿勢」も含めてリテラシーの高低が判断される点に注意が必要です。
なぜ今、企業にとってデジタルリテラシーが重要なのか
 デジタル技術の進化とともに、企業の競争力は「どれだけテクノロジーを活用できるか」に大きく左右されるようになっています。もはやIT部門や一部の専門職だけでなく、すべての従業員が一定のデジタルスキルを持ち、変化に柔軟に対応する力が求められる時代です。
デジタル技術の進化とともに、企業の競争力は「どれだけテクノロジーを活用できるか」に大きく左右されるようになっています。もはやIT部門や一部の専門職だけでなく、すべての従業員が一定のデジタルスキルを持ち、変化に柔軟に対応する力が求められる時代です。
ここでは、企業にとってデジタルリテラシーが重要となっている背景を2つの観点から解説します。
DXを推進させるため
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質は、単なるIT導入ではなく、業務やビジネスモデルを抜本的に見直し、価値創造のあり方を変えることにあります。しかし、どれだけ最新のツールやシステムを導入しても、それを使いこなす人材のスキルが不足していれば、DXは形骸化してしまいます。
社員一人ひとりがDXを自分ごととして考え、相応のデジタルリテラシーを身につけることが、DX成功の第一歩となります。
DXの定義や基本情報については、以下の記事で詳しく紹介しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義や事例・成功のポイントを紹介
働き方・ビジネススタイルの変化に対応するため
コロナ禍をきっかけにテレワークやオンライン会議、クラウドを活用した業務管理など、働き方が急速に変化しました。同時に、顧客との接点もデジタル化が進み、非対面での営業・接客・サポートが当たり前になりつつあります。
このような環境では、社員全員がデジタルツールやクラウドサービスを使いこなし、柔軟に変化へ対応できることが重要です。ビジネスの生産性とスピードを落とさず、持続的に成長するためには、全社的なデジタルリテラシーの底上げが不可欠と言えるでしょう。
デジタルリテラシーが低いと発生しがちな課題
社員のデジタルリテラシーが十分に育っていない企業では、さまざまな問題が表面化しやすくなります。これらは一時的なミスやトラブルにとどまらず、企業全体の業務効率やブランド価値、そして競争力にまで悪影響を及ぼすこともあります。
ここでは、デジタルリテラシーが低いことで起きがちな3つの代表的な課題を紹介します。
新しいシステムやツールに対する拒否感
デジタルに不慣れな社員が多い職場では、新しいITツールや業務システムの導入に対して「難しそう」「慣れているやり方がいい」といった心理的な抵抗が起きやすくなります。
結果として、せっかく導入したDX施策が活用されず、形だけの改革に終わってしまうケースも少なくありません。こうした変化への拒否感は、組織の成長スピードを大きく鈍らせる要因となります。
セキュリティや個人情報のリスク管理が不十分
パスワード管理やファイルの取り扱い、クラウドサービスの共有設定など、日常業務の中にも情報漏えいや不正アクセスにつながるリスクは潜んでいます。デジタルリテラシーが低いと、こうした基本的なセキュリティ対応ができず、内部からの情報流出やサイバー攻撃の被害を招くリスクが高まります。
これは顧客や取引先の信頼にも大きく影響するため、企業にとって深刻な課題です。
他社と比べて競争力を失いやすくなる
市場や顧客ニーズの変化に対応し続けるためには、業務のデジタル化・自動化、データ活用、オンラインでのマーケティング活動などが必要不可欠です。
ところが、社員のデジタル対応力が不足していると、こうした変化にスピーディに追いつくことができず、他社と比べて業務効率や顧客対応力で後れを取ってしまいます。デジタルリテラシーの不足は、結果的に企業の競争力低下へと直結するのです。
社員のデジタルリテラシーを高める方法
 企業全体でデジタル変革を進めるには、社員一人ひとりのデジタルリテラシーの底上げが欠かせません。従業員のスキル習得を効果的に促すためには、複数の手段を組み合わせて取り入れることが重要です。以下に、代表的な4つのアプローチとその特徴を紹介します。
企業全体でデジタル変革を進めるには、社員一人ひとりのデジタルリテラシーの底上げが欠かせません。従業員のスキル習得を効果的に促すためには、複数の手段を組み合わせて取り入れることが重要です。以下に、代表的な4つのアプローチとその特徴を紹介します。
社内研修
eラーニング・資格取得の推奨
OJTでの実務トレーニング
外部研修サービスの活用
社内研修
社内研修は、自社の業務内容や課題に即した内容で構成できるため、実務との親和性が高い点がメリットです。特定部署に限定せず全社的に実施すれば、部門間での意識共有にもつながります。
ただし、講師の確保や教材設計、スケジューリングなど準備に手間がかかる点が課題です。さらに、運営の負荷が大きいと、形骸化するリスクもあるため注意が必要です。
eラーニング・資格取得の推奨
オンライン講座や外部資格制度を活用する方法は、自学自習型で導入しやすく、コストも比較的低いのが特徴です。受講履歴やテスト結果などから習熟度の可視化もしやすく、継続的な学習支援にも適しています。
一方で、社員の主体性に依存しやすく、実務への定着が弱くなることもあるため、フォローアップ施策と併用することが望ましいでしょう。
OJTでの実務トレーニング
現場業務に即したOJT(On the Job Training)は、実際の業務を通じてスキルを学べるため、即戦力化しやすい育成方法です。特に新しいツールやシステムを現場で導入するタイミングで有効です。ただし、指導者のスキルや教え方に依存するため、属人的な育成になりやすく、全社的な底上げには向かない場合もあります。
外部研修サービスの活用
育成設計から講義、効果測定までを一括で支援してくれる外部研修サービスは、リソースが限られた企業にとって非常に有効です。専門的なカリキュラムによって短期間でのスキル向上や意識改革が期待できるほか、最新トレンドや事例を交えた体系的な教育が可能です。全社的なデジタルリテラシーの底上げにも効果的で、企業規模を問わず導入が進んでいます。
DX人材の育成には、プロによる研修サービスの導入がおすすめです。
累計4,000社以上の支援実績を持つ「リンプレス」によるDX推進人材育成プログラムの詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。御社の課題に合わせて、最適なカリキュラムをご提案いたします。
社員のデジタルリテラシーの底上げには「リンプレス」
「自社のDX人材育成をプロに任せたい」とお考えなら、4,000社に導入された実績があるリンプレスにお任せください。
リンプレスでは、基礎的なDXリテラシーから、IT企画力を身につける上流工程まで、幅広いDX研修プログラムを提供しています。また、研修プログラムだけではなくDXの内製化を支援するコンサルティングサービスも行っているため、御社のDX課題をまとめて解決いたします。
「DXリテラシー研修」とは
リンプレスの「DXリテラシー研修」は、DXリテラシー標準に準拠した内容で構成されており、全社員がDXを正しく理解し自ら行動できるよう支援する研修プログラムです。
Why・What・How・マインドの4領域を体系的に学べる構成となっており、DXに関する前知識無しで誰でも受講できる、DX入門研修として最適な内容となっています。
業界や業種を問わず、全社的なDX推進の基盤づくりに役立ちます。
リンプレスのDXリテラシー研修|導入事例
リンプレスの「DXリテラシー研修」を導入した、ヤマエグループホールディングス株式会社の事例を紹介します。
同社は、"攻めのDX"として「ビジネスプロセスの最適化」や「業務のデジタル化」「データ活用の促進」などの目標を掲げていましたが、全社員のDX・ITリテラシーが低いという課題を抱えていました。
メイン事業である食品の卸売業はアナログな仕事が多く、デジタル化できていない部分が多くあったためです。そこで、最新の技術を駆使して業務やビジネスプロセス自体を効率化し、コスト削減や生産性向上につなげていくため、グループ約70社全体の意識改革やリテラシーレベルの底上げが重要であると考え、リンプレスの研修を導入いただきました。
決め手となった最大のポイントは、企業の要望に応じて、研修プログラムを柔軟にカスタマイズできるという点です。
DXリテラシー研修の実施後、受講した社員から「今後も定期的にやってほしい」「会社が求めるスキルやレベル感が理解できた」「社員だけではなく派遣社員やパート社員にも受講させたい」といった前向きな意見を多くいただきました。
こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。
DX実現に向けた"変革マインド"を醸成!ヤマエグループが目指す「全社員デジタル人財化」に向けた取り組み
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
まとめ
デジタルリテラシーは、業種や職種を問わず全社員に求められる基礎スキルです。DX推進や新たな働き方への対応、セキュリティ意識の向上など、現代のビジネスにおいて不可欠な要素となっています。一方で、社内での育成には設計・実施の手間や限界が伴うため、外部の専門サービスを活用することも有効です。
リンプレスでは、経済産業省のデジタルスキル標準に準拠した「DXリテラシー研修」を提供しており、組織全体のリテラシー向上を効率的に支援します。変化に強い組織をつくるために、今こそ社員のデジタル基盤力を高めていきましょう。