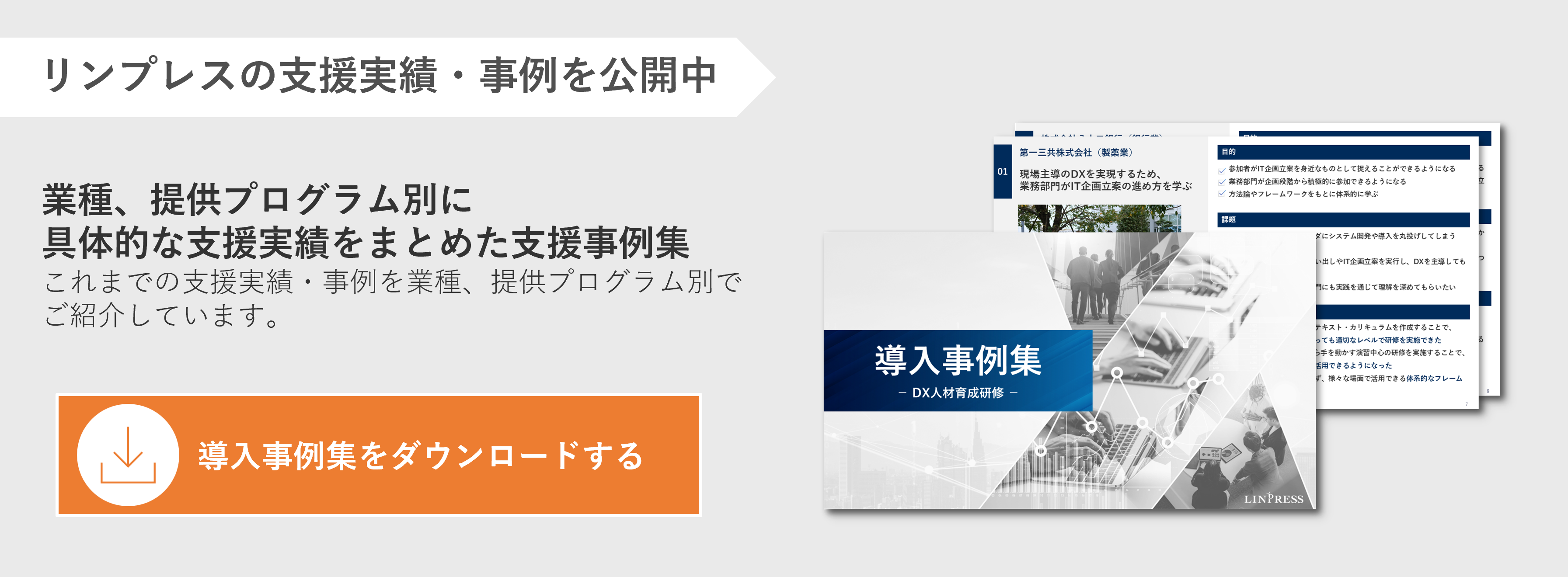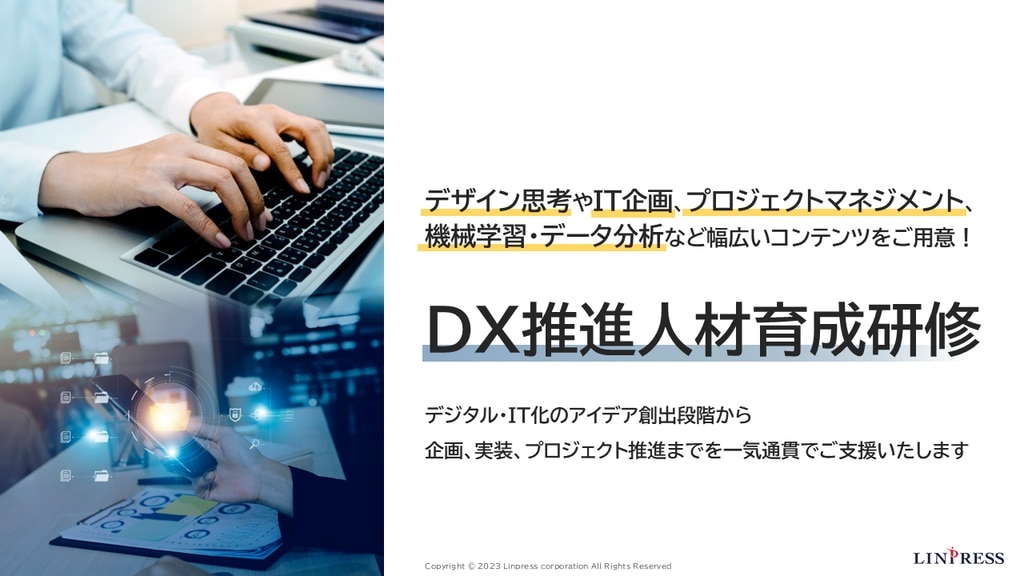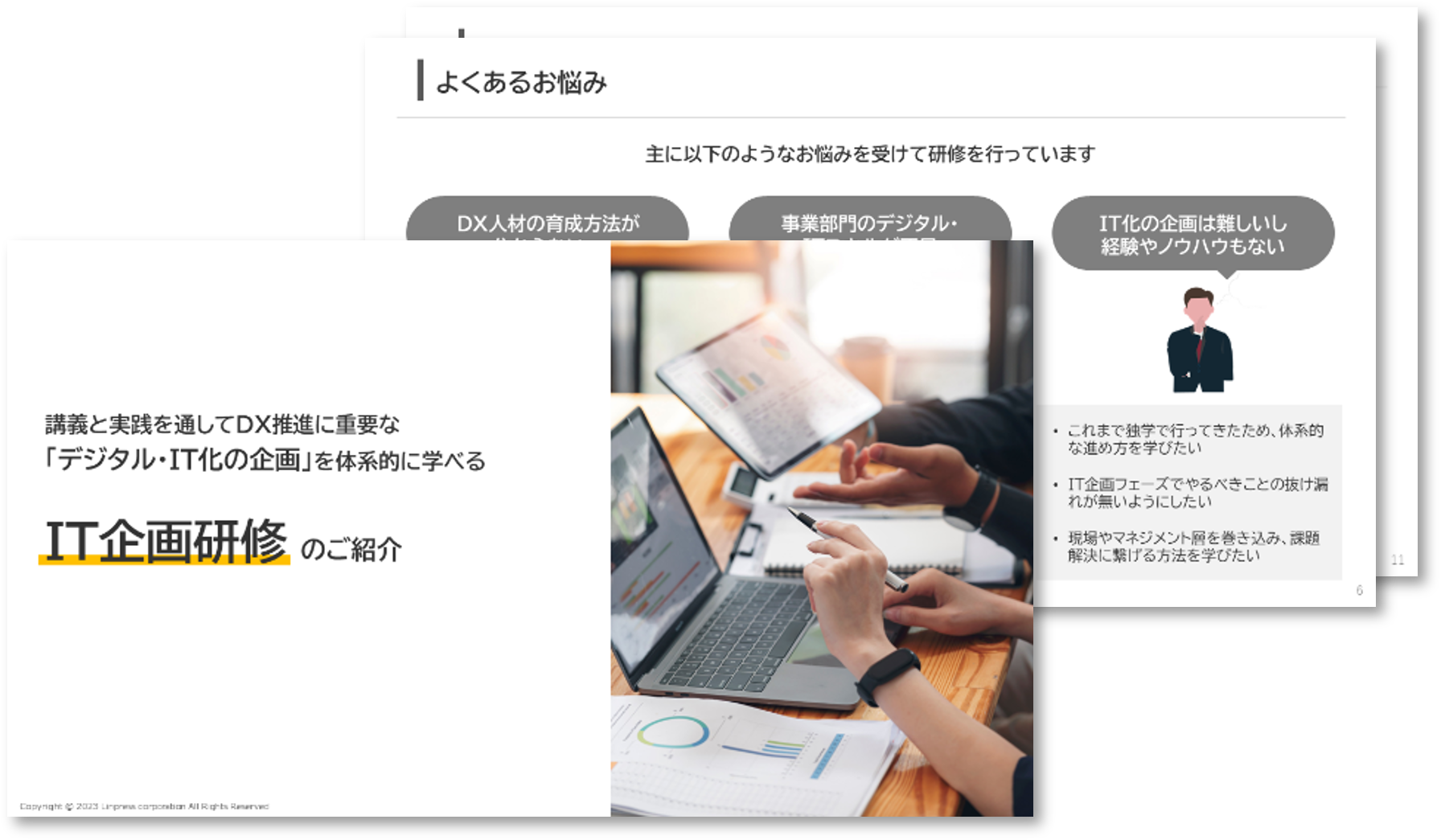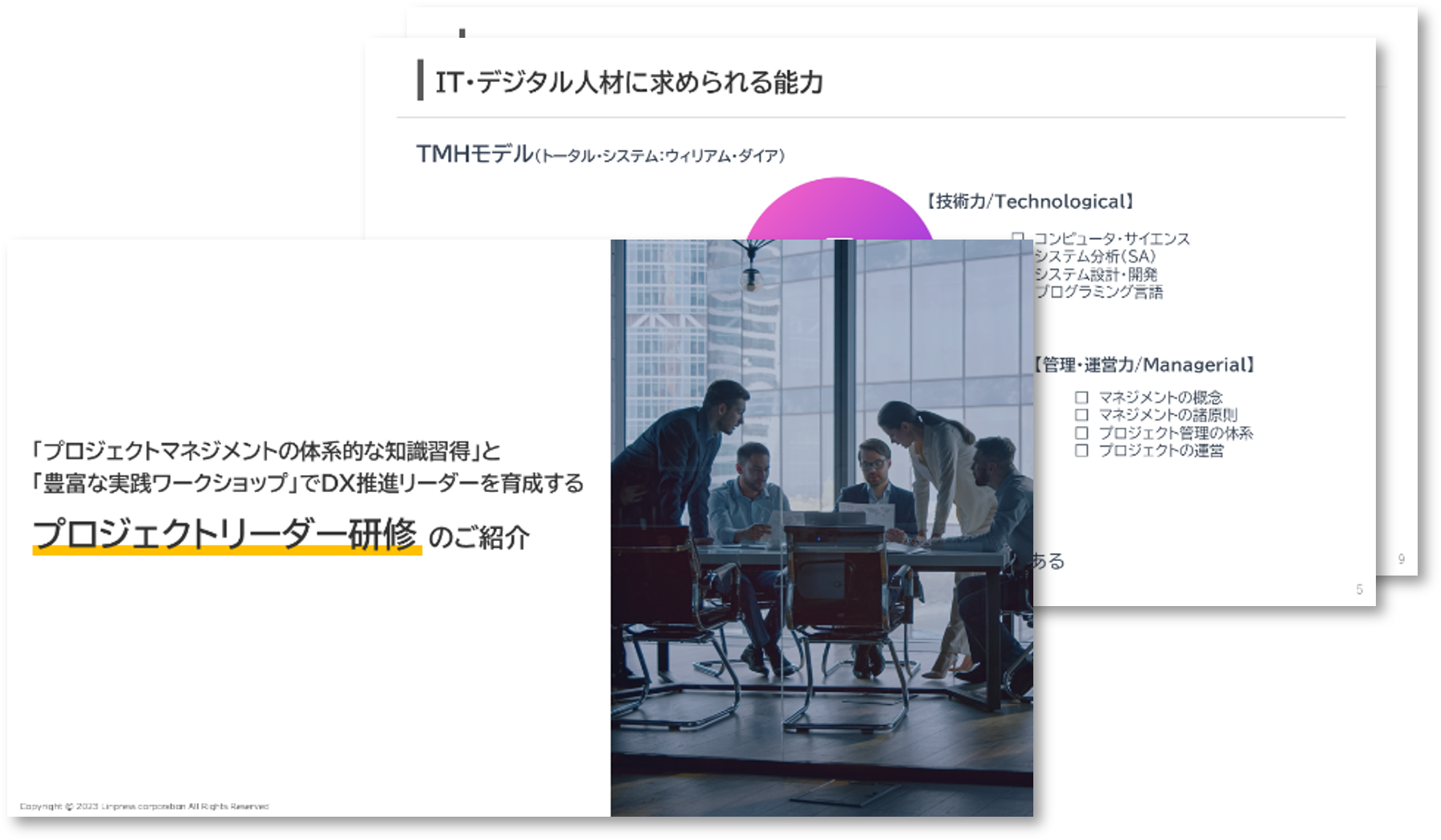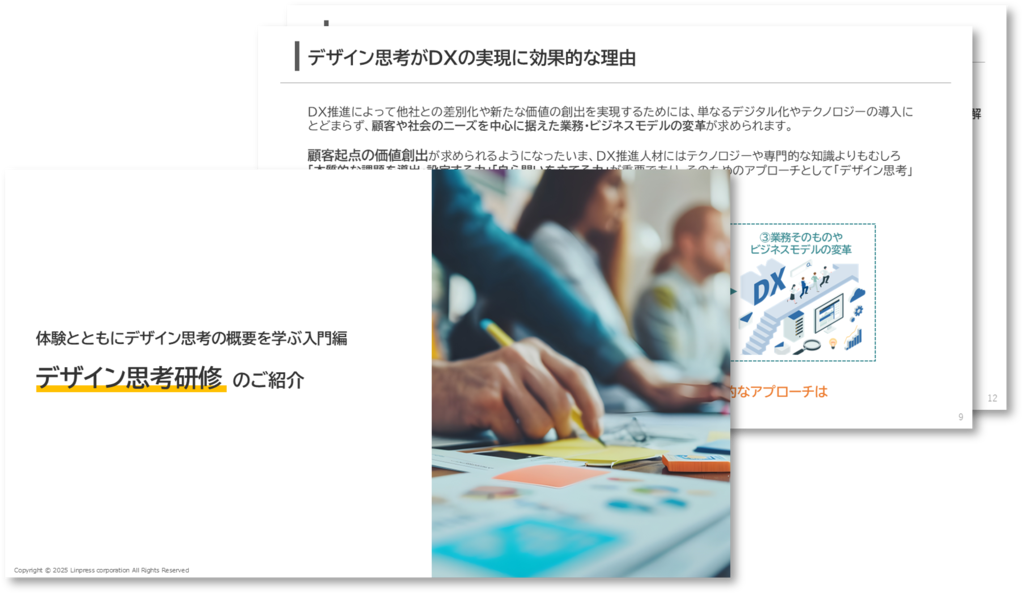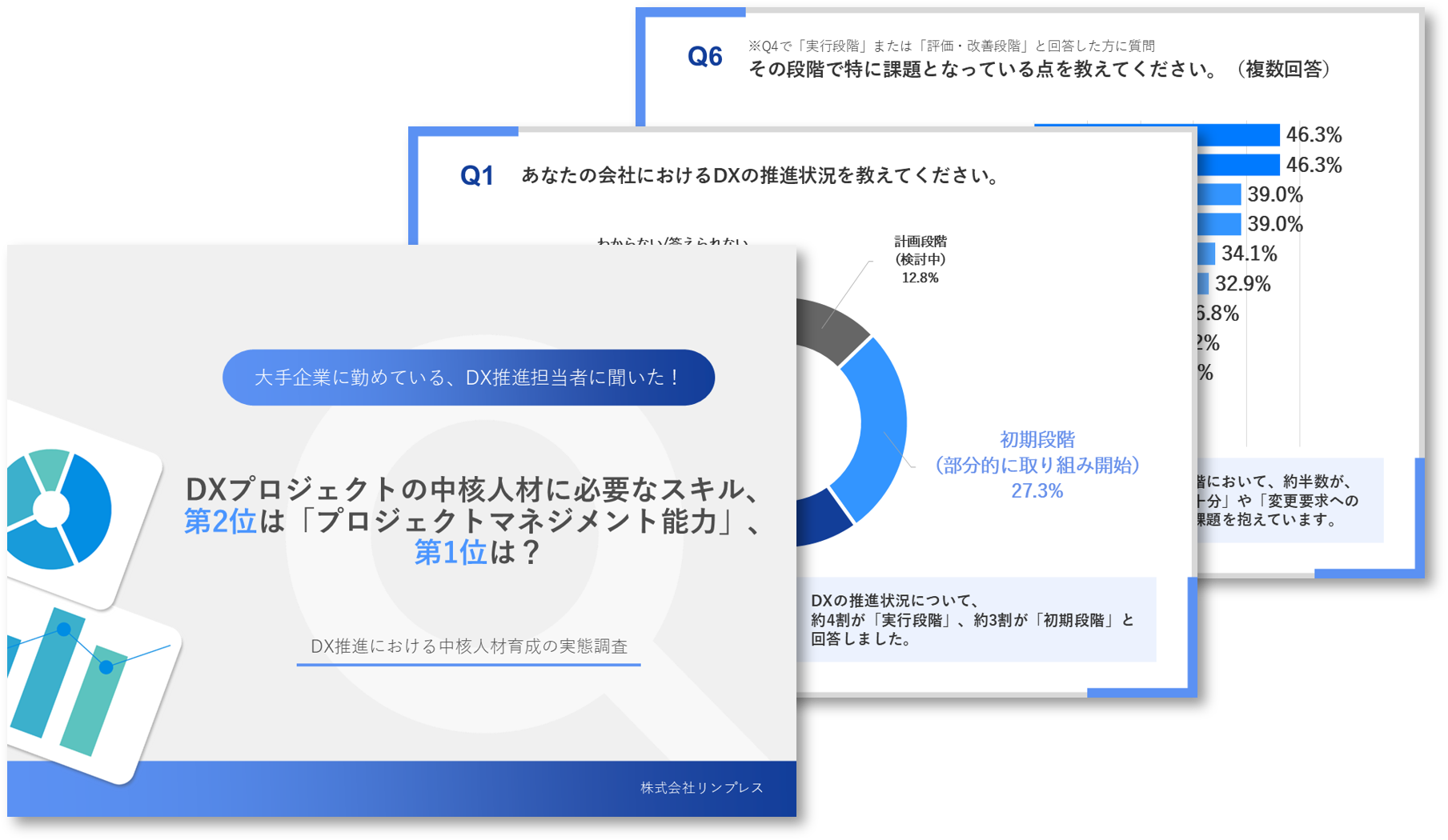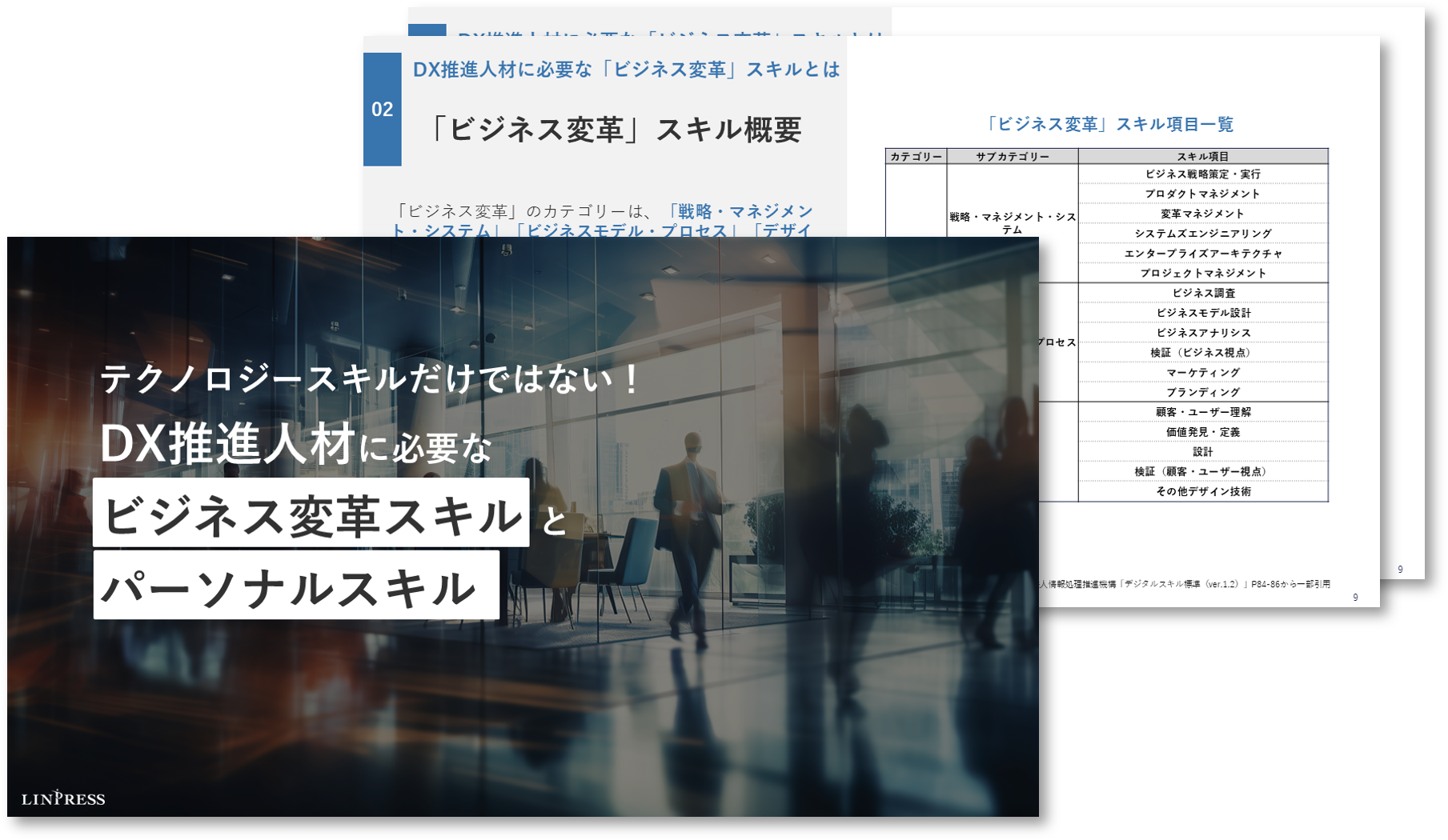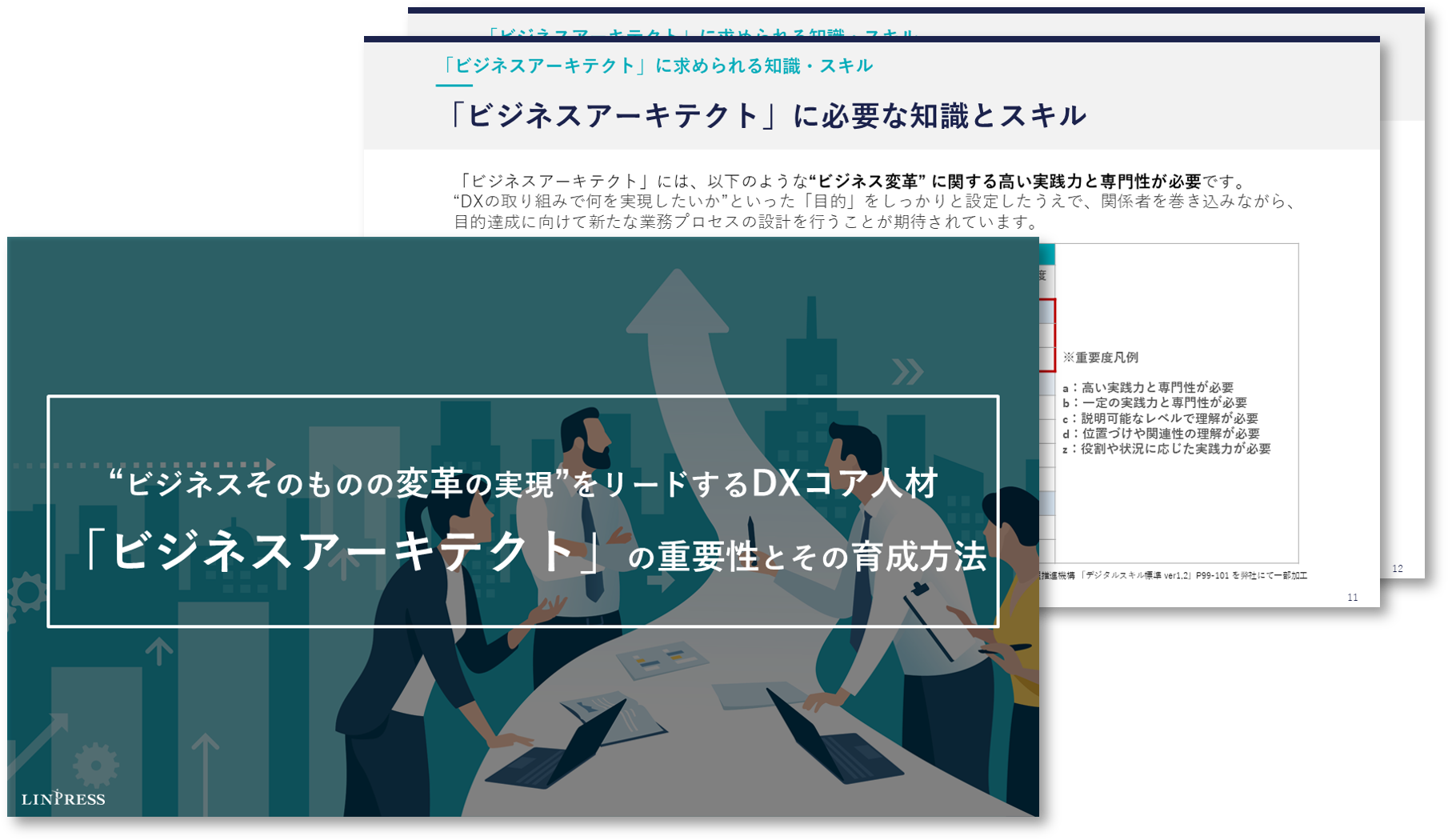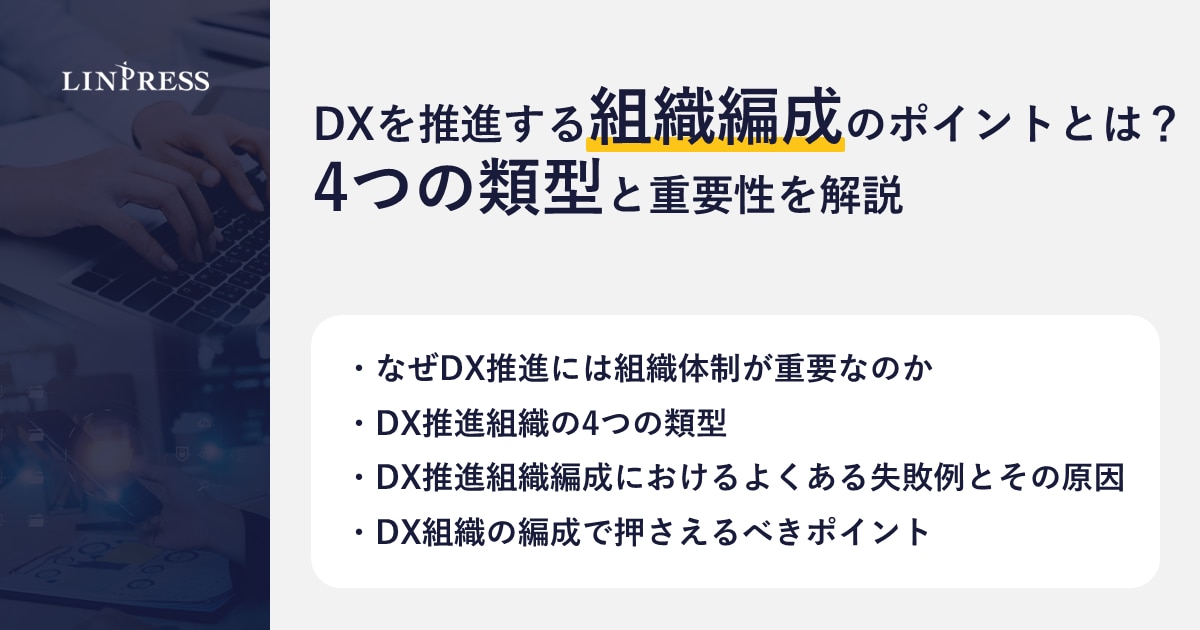
DXを推進する組織編成のポイントとは?4つの類型と重要性を解説
DXを進めるうえで、技術や戦略だけに注目が集まりがちですが、実際の成功を左右するのは「組織体制」です。どのような組織編成で臨むかによって、DXの成果や定着率には大きな差が生まれます。
本記事では、DX推進に必要な組織設計の重要性や代表的な4つの組織類型、よくある失敗例とその対策について解説します。
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
なぜDX推進には組織体制が重要なのか
DXを成功に導くためには、戦略やツールだけでなく、それを実行・定着させる組織体制の整備が不可欠です。
企業におけるDXは一部門の業務改善にとどまらず、経営層から現場までを巻き込んだ全社的な変革活動です。したがって、誰が推進するのか、どのように各部門と連携するのかといった組織設計がDXの成果に直結します。
以下では、その理由を3つの観点から解説します。
DXは全社横断型の取り組みであるため
DXは営業や製造、総務など一部の部門に閉じた取り組みではなく、企業全体にまたがる仕組み・文化・価値提供の変革を伴うプロジェクトです。そのため、各部門がバラバラに動いては非効率であり、連携を促進する横断的な組織体制が必要になります。
全社レベルでのビジョン共有や意思決定を実現する体制整備こそが、DX推進の土台となります。
部門任せでは属人化・部分最適に陥りやすいため
DXを特定部門や担当者に任せきりにすると、属人化やその部門内での完結にとどまり、企業全体の変革にはつながりにくいという課題があります。加えて、他部門との連携やデータの統合が不十分なまま部分最適に陥る危険性もあります。
これを防ぐには、経営層の関与を含めた明確なDX体制設計が欠かせません。
DX推進の風土を醸成するため
どれだけ戦略や技術が整っていても、組織の中に変化を受け入れる文化や新しい挑戦を歓迎する風土がなければ、DXは定着しません。推進組織が旗振り役となり、部門間の調整や社内啓発、ナレッジ共有を行うことで、社内に変革の意識を根付かせることができます。
社内でDX推進組織を編成することは、DXのスピードと継続性を支える重要な基盤となるでしょう。
DX推進組織の4つの類型
 DXを円滑かつ持続的に進めるためには、自社に合った推進体制の選定が重要です。推進体制にはいくつかの代表的なパターンが存在し、それぞれに強みと注意点があります。
DXを円滑かつ持続的に進めるためには、自社に合った推進体制の選定が重要です。推進体制にはいくつかの代表的なパターンが存在し、それぞれに強みと注意点があります。
ここでは、企業が選択しやすい4つのDX推進組織の類型を紹介し、その特徴と導入時のポイントを解説します。
1.経営企画部門推進型組織
経営企画部門がDXの中核を担うケースの組織体制です。
全社的な経営戦略との連動が取りやすく、中長期的な視点でDXを推進できるメリットがあります。社内の各部門を俯瞰して調整しやすい一方で、現場との距離が生まれやすいため、実行力を高めるためには現場との密な連携が求められます。
2.各事業部門推進型組織
営業や製造、開発などの各事業部門ごとにDXを推進する組織体制です。
現場課題に即した対応ができ、スピード感を持って施策を打てる点が特徴です。ただし、部門間で方針が異なり、全社最適が図りづらくなる傾向もあるため、統一的なビジョンの共有や横串の調整機能が必要です。
3.IT部門推進型組織
IT部門がDXの中心となり、システム導入やインフラ整備を主導する組織体制です。
技術的な実装力や既存システムとの整合性確保に強みがあります。ただし、技術主導に偏ると業務部門のニーズと乖離する恐れがあるため、業務部門との対話やプロセス理解に注力する必要があります。
4.組織新設型組織
CDO(Chief Digital Officer)やDX推進室など、新たな組織を立ち上げてDXを専門的に推進するスタイルです。経営直下での迅速な判断や、部門横断でのリードがしやすい点が魅力です。ただし、社内に浸透させるには他部門との協働や影響力の確保が必要で、組織全体との橋渡し役が求められます。
DX推進の組織編成|よくある失敗例とその原因
どれだけDXの戦略や技術が優れていても、それを実行する組織体制に課題があると、期待された成果は得られません。実際に多くの企業が陥りやすい失敗パターンには、組織設計や運用の不備が根本にあることが少なくありません。ここでは、よくあるDX推進組織の失敗例とその背景を以下の4つの視点から紹介します。
「名前だけの推進室」で実権がない
部門間の対立・協力不全による足踏み
DXの目的が曖昧で組織の機能が分散
初期の成功後に継続体制が崩れてしまう
「名前だけの推進室」で実権がない
「DX推進室」や「デジタル戦略室」などの名称があっても、実際には権限や予算がなく、形だけの存在にとどまってしまうケースがあります。
経営層の支援が得られず、各部門との調整力も弱い状態では、施策を具体化する前に組織が形骸化してしまう危険があります。名だけでなく実質的な機能を備えた体制づくりが求められます。
部門間の対立・協力不全による足踏み
DXは部門横断での取り組みが必要ですが、部門ごとの利害対立や縄張り意識が原因で連携が進まず、プロジェクトが停滞する例もあります。
特にデータ共有や業務標準化の場面では、対立が顕在化しやすく、調整役の不在が失敗の引き金になります。共通目標と調整力を担う組織が不可欠です。
DXの目的が曖昧で組織の機能が分散
DXの目的や方向性が明確でないまま組織が編成されると、部門間で取り組みの優先順位がばらつき、成果が断片化してしまいます。
結果として「何のためにやっているのか分からない」という空気が生まれ、推進力が失われてしまいます。目的と役割を明確に定義したうえでの組織設計が重要です。
初期の成功後に継続体制が崩れてしまう
DXプロジェクトの初期フェーズでは成功を収めたものの、その後推進人材の異動や予算縮小などにより継続体制が崩れ、定着せずに終わる例も見られます。
一過性の取り組みにしないためには、長期的な視野での体制整備と、成功事例の社内共有・再現性の確保が欠かせません。
DX推進組織を編成する際に役立つ「チームビルディング」のコツは、以下の記事で詳しく紹介しています。
チームビルディングとは?5つの段階とおすすめの手法を簡単に解説
DX組織の編成で押さえるべきポイント
 DXを成功に導くためには、技術やビジョンだけでなく、それを実行に移すための組織体制づくりが不可欠です。全社的な推進体制を整備するうえで、無理なく継続可能な仕組みと、柔軟性を持った組織運営の両立が求められます。ここでは、DX組織を編成・運用する際に押さえておきたい実務的なポイントを5つ紹介します。
DXを成功に導くためには、技術やビジョンだけでなく、それを実行に移すための組織体制づくりが不可欠です。全社的な推進体制を整備するうえで、無理なく継続可能な仕組みと、柔軟性を持った組織運営の両立が求められます。ここでは、DX組織を編成・運用する際に押さえておきたい実務的なポイントを5つ紹介します。
スモールスタートで段階的に体制を整備する
最初から大規模なDX推進体制を整えようとすると、実行段階での混乱やリソース不足を招きやすくなります。
まずは限られた範囲で施策を実行し、小さな成功を積み上げることで、組織の理解と協力を得る形が現実的です。徐々に体制や対象業務を拡大しながら、全体最適を目指しましょう。
経営層のコミットメントを明確にする
DX推進には企業文化や価値観の変革も伴うため、組織編成にあたっては経営トップの明確な意思表明と継続的な関与が欠かせません。
トップが積極的にDXの意義を発信し、組織全体に方向性を示すことで、現場の納得感と行動が生まれます。また、経営層が自らDX推進に関わり、リーダーシップを発揮することで、現場との信頼関係も築かれやすくなります。
権限やリソースの明確化・調整を行う
DX推進部門や担当者に与えられる権限や予算が不明確だと、他部門との調整が難航し、実行力が損なわれます。組織内での役割分担や意思決定権の所在、使用可能なリソースなどを明確にし、あらかじめ調整しておくことが重要です。
特に横断的な取り組みでは、リソースの融通が柔軟に行える仕組みが求められます。
現場巻き込みと並行してDX人材育成を進める
現場を巻き込まずにDXを進めると、実態に合わない施策になりがちです。現場担当者の協力を得ながら業務改革を進めると同時に、将来を見据えたDX人材の育成にも取り組む必要があります。
OJTや外部研修などを活用し、技術力だけでなく変革推進力を持つ人材を育てることが、持続的な体制構築につながります。
DX人材を育成するコツについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
DX人材を育成する5つのステップ|おすすめの研修プログラムと事例も紹介
DX人材の育成には、プロによる研修サービスの導入がおすすめです。
累計4,000社以上の支援実績を持つ「リンプレス」によるDX推進人材育成プログラムの詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。御社の課題に合わせて、最適なカリキュラムをご提案いたします。
リンプレスのDX推進人材育成プログラム
外部アドバイザーを加えて客観的視点を持つ
自社内だけでDXを進めると、業界の常識や既存の業務にとらわれがちです。外部のDXコンサルタントや有識者を巻き込むことで、客観的な視点や専門知識を取り入れやすくなります。
特に初期段階では、外部からの知見を活用することで方向性のブレを防ぎ、スピーディかつ効果的な体制構築が実現しやすくなります。
DX内製化のお悩みはリンプレスへ
DXを推進するうえで、「外注だけでは限界がある」「自走できる体制をつくりたい」といった課題を抱える企業も少なくありません。内製化を成功させるには、実行できる人材と、組織に定着させる仕組みの両輪が必要です。リンプレスでは、企業の状況に応じて最適な伴走支援を行い、社内にノウハウを蓄積できる体制づくりをサポートします。
DX人材育成プログラム
リンプレスでは、現場で実践できるDXスキルの習得に特化した育成プログラムを提供しています。データ活用や業務改革の基礎から、プロジェクト推進に必要なマネジメント力まで段階的に育成することで、自社内にDXをリードできる人材を育てます。講義形式だけでなく、実務への応用を前提としたワークショップも組み込まれており、学んだ内容をすぐに現場に活かせる構成です。
DXコンサルティング
戦略策定から業務改革、システム選定や定着支援まで、リンプレスは一貫したDXコンサルティングを提供します。単なるアドバイスにとどまらず、クライアントのチームに伴走しながら成果を出す実行支援型のスタイルが特徴です。企業文化や業界特性に合わせた柔軟な提案が可能で、既存のリソースを最大限に活かす形でのDX推進が実現できます。
DXコンサルティングに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
DXコンサルティングとは?支援内容や選び方、導入すべきメリットを詳しく解説
リンプレスのDX人材育成を導入した企業の事例
実際にリンプレスの研修サービスを導入した企業の事例を紹介します。
株式会社八十二銀行
株式会社八十二銀行では、自社内にシステム開発部門があり、新しいシステムを作る際は事業部門と開発部門がともに開発を行っています。しかし近年、どちらの部門も多忙となり、意思疎通がうまくいかず手戻りが発生するという課題が発生していました。この原因の一つに、元々の目的の設定と、経営的な視点で論理立てて工程を組み立てることができていない上流工程に問題があるのではないかと考えます。そこで、論理的に課題を整理しながら、企画を進めるフレームワークに沿って学べるリンプレスのIT企画研修を導入いただきました。
結果として、受講者の8割が研修の内容に満足し、9割以上の受講者が実際の業務に役立つと回答していただいたという、大変満足度の高い研修が実施できました。
こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。
株式会社八十二銀行様の事例|事業部門自らデジタル・IT化を企画し、スピード感のあるDXの実現へ
第一三共株式会社
第一三共株式会社では、業務部門において自ら課題の洗い出しができておらず、システムによってどのようなことを解決したいのかが明確になっていないという問題がありました。業務部門にもIT企画立案力を身につけさせるため、リンプレスのインハウス研修「IT企画研修」を導入いただきました。
リンプレスならではの、実際の業務に近い内容で学べる研修カリキュラムに大変ご満足いただき、参加者から「参考になった」「受講してよかった」というお声を多くいただきました。
こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。
第一三共株式会社様の事例|現場主導のDXを実現するため、業務部門がIT企画立案の進め方を学ぶ
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
まとめ
DX推進において、組織体制の整備は成功の可否を分ける大きな要素です。「推進組織は設けたが機能していない」「初期はうまくいったが継続できない」など、よくある課題には共通する構造的な問題があります。経営層の関与、現場との連携、スモールスタートからの段階的整備など、押さえるべきポイントを意識しながら体制構築を進めましょう。また、外部の支援を活用することで、社内にノウハウを定着させる近道にもなります。リンプレスは、実行力と定着力を備えた組織づくりをサポートします。
<文/文園 香織>