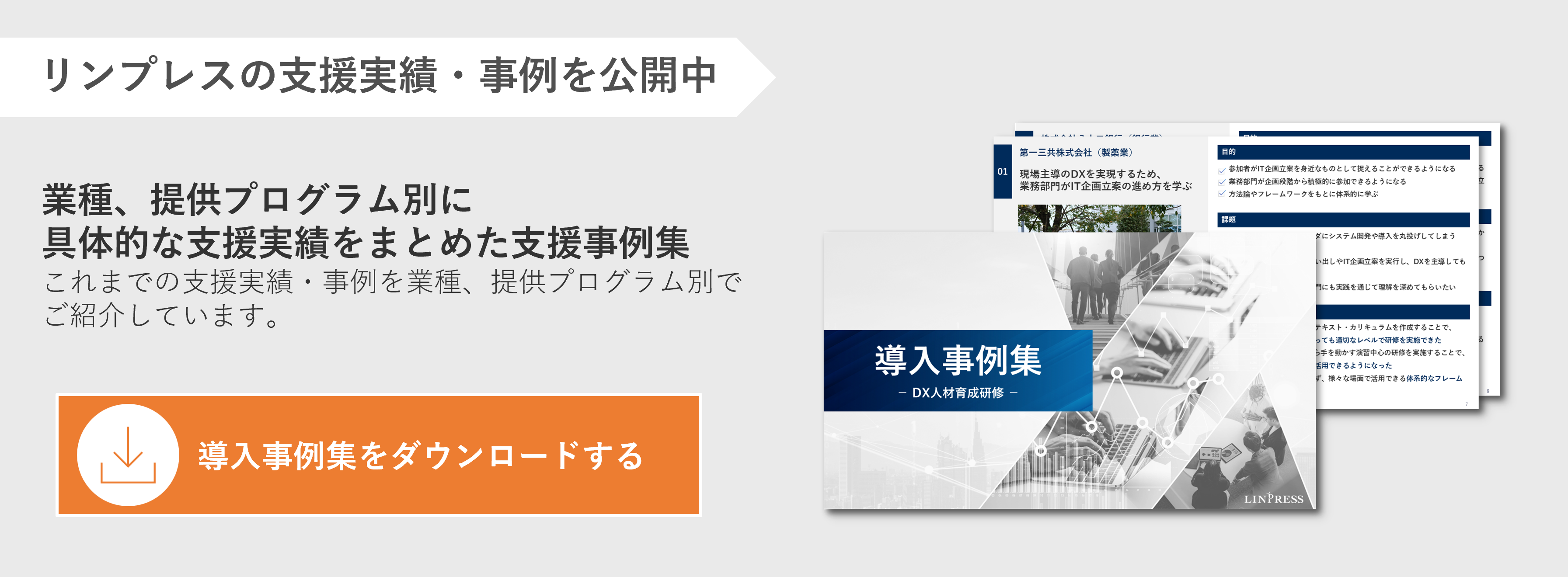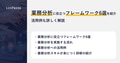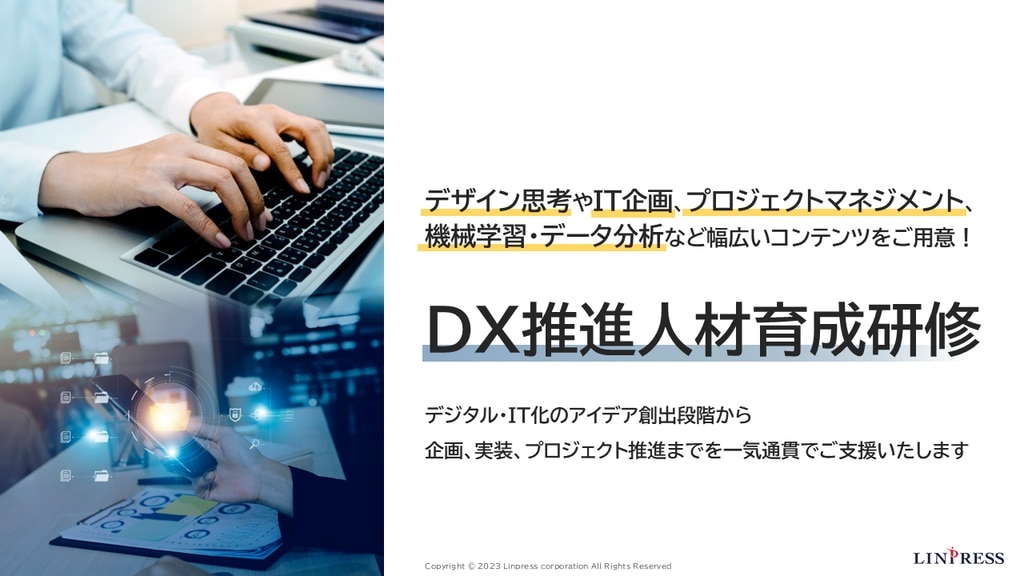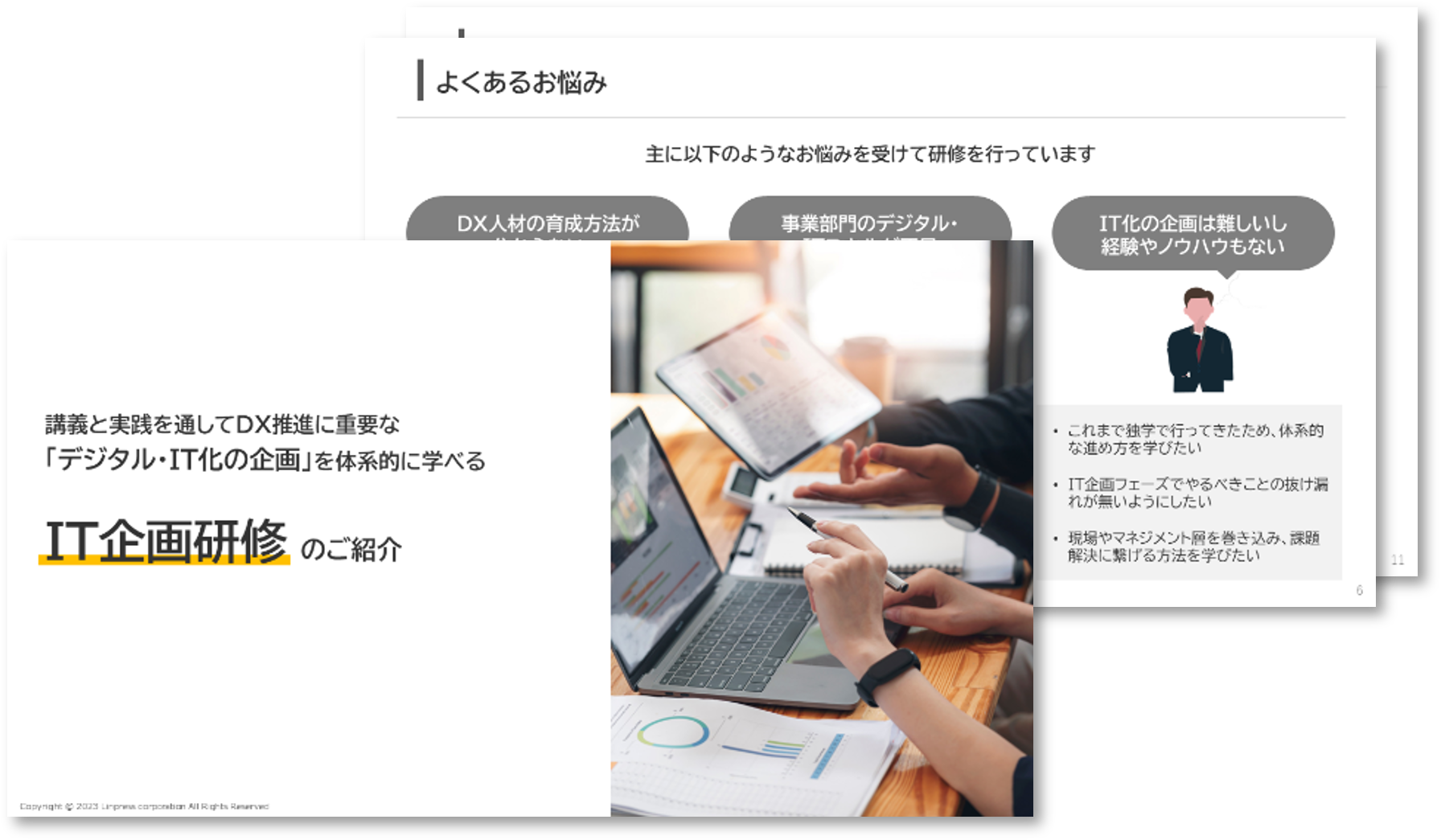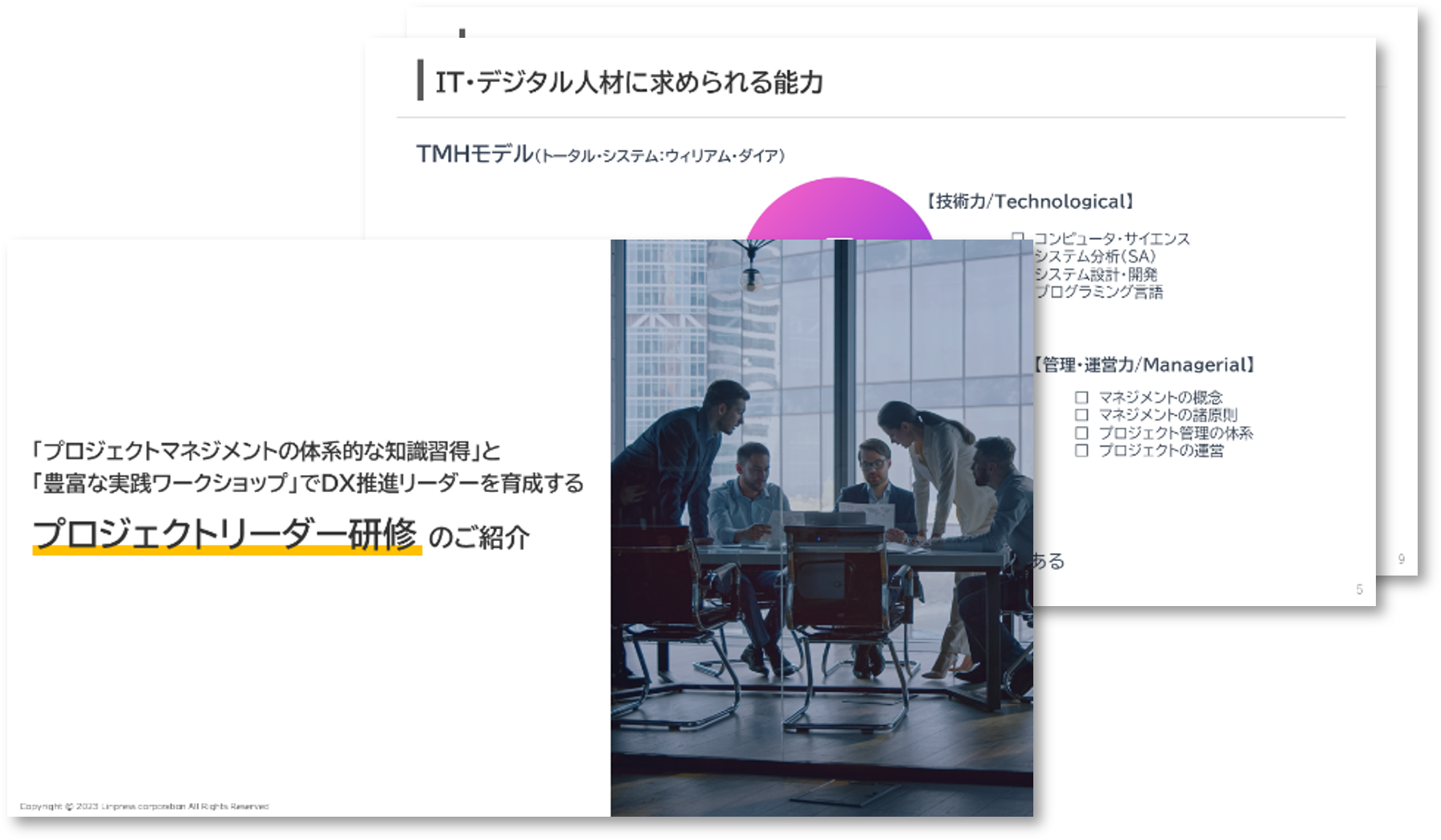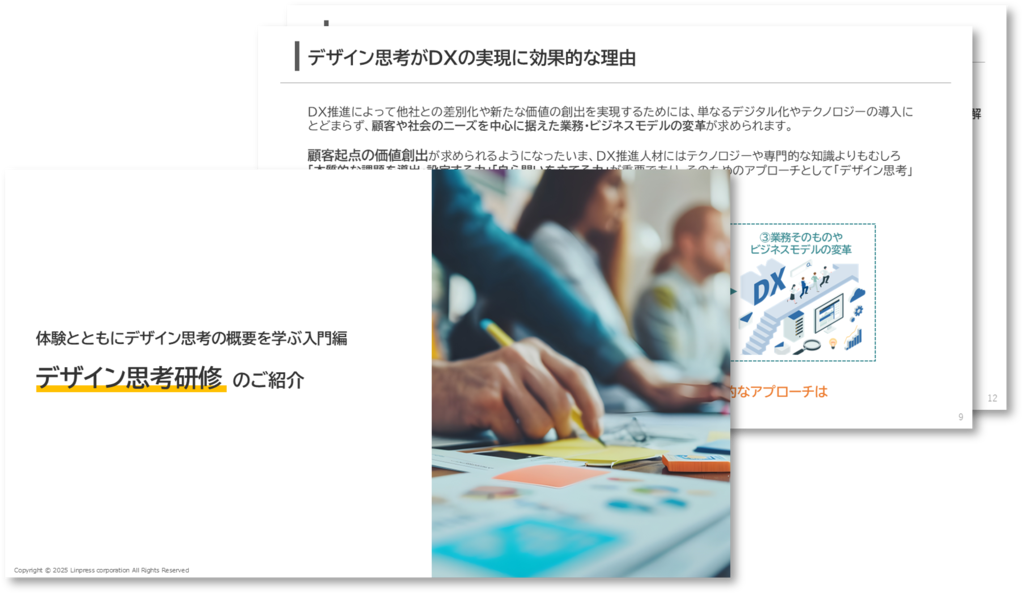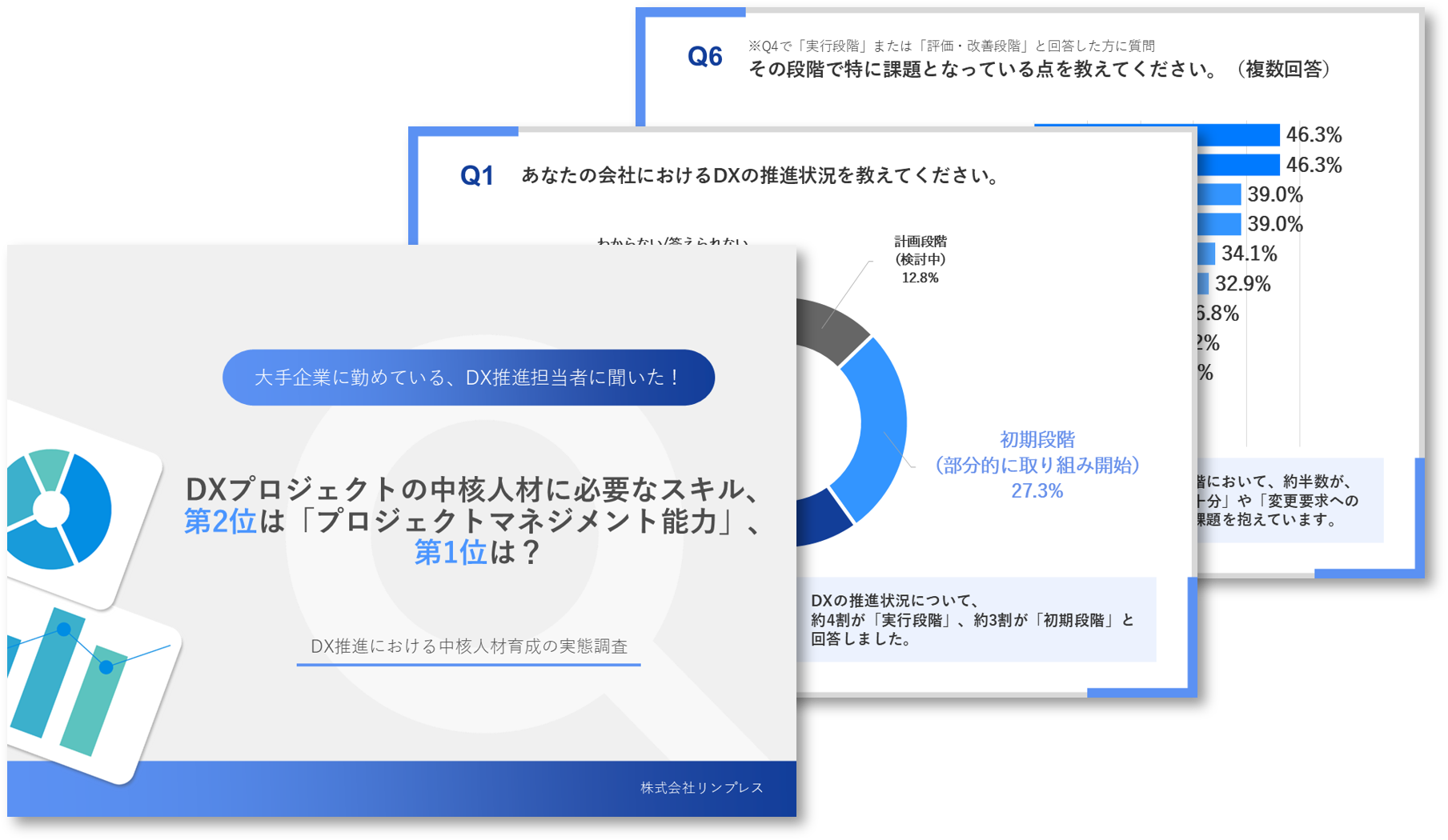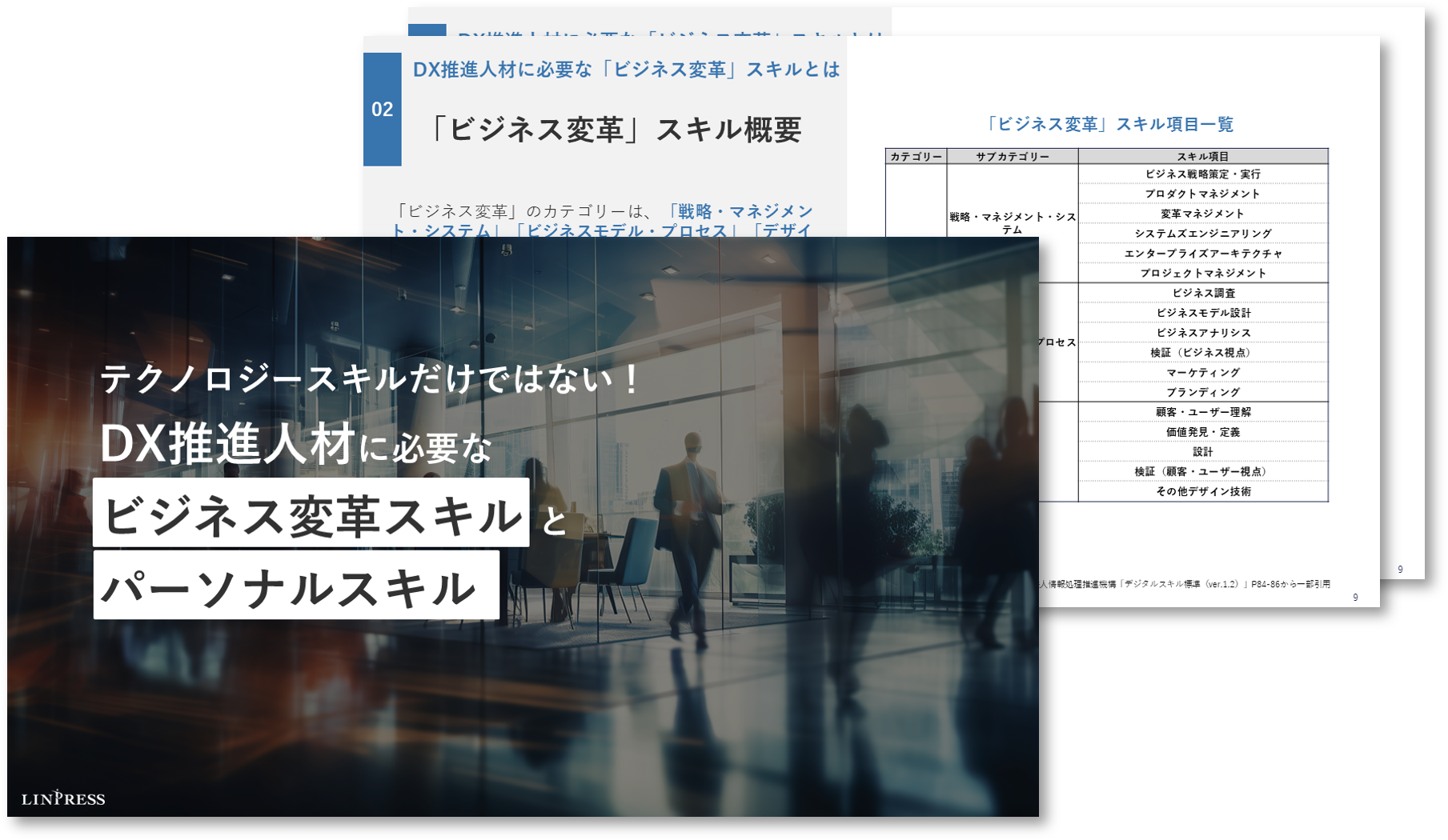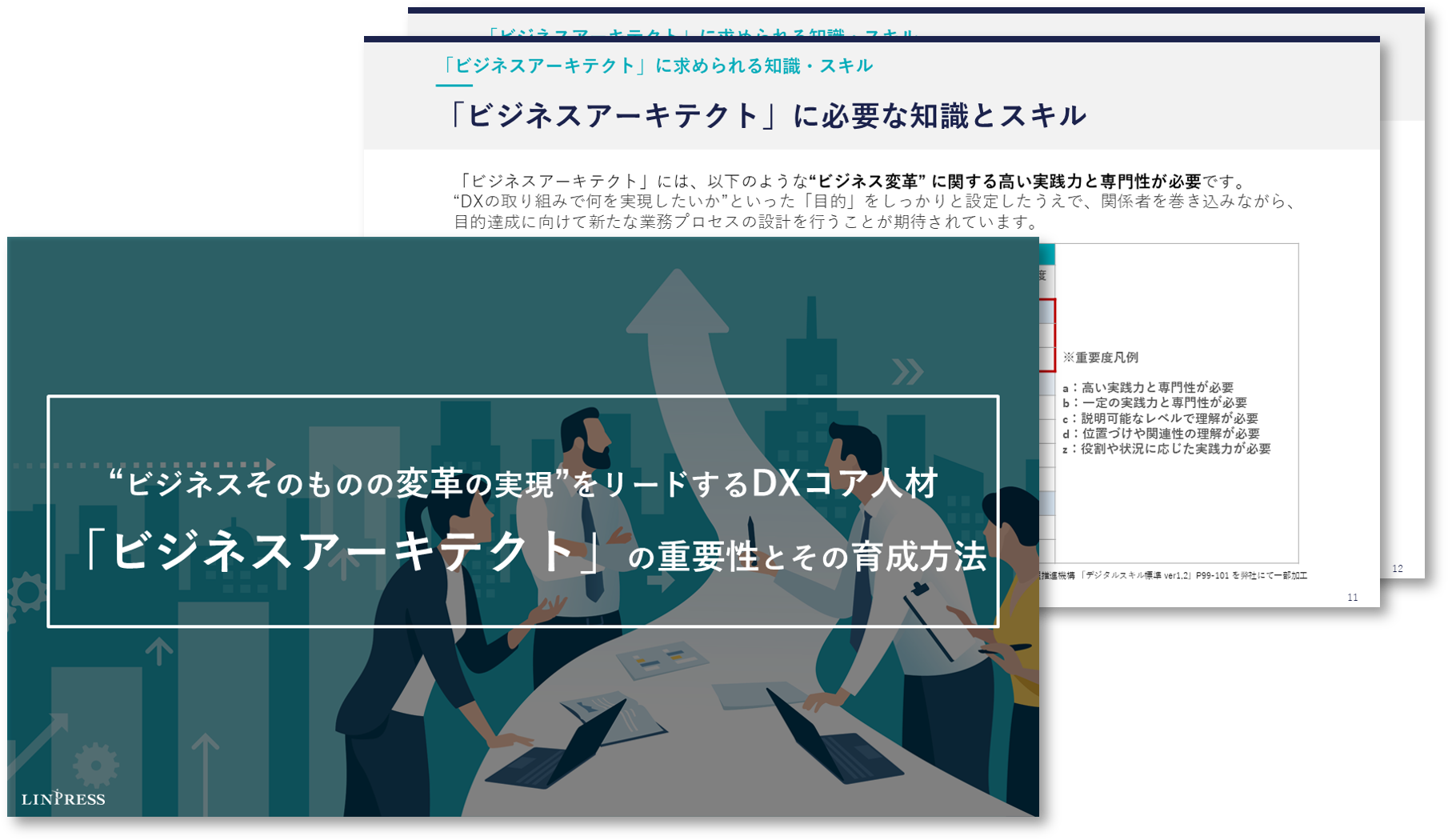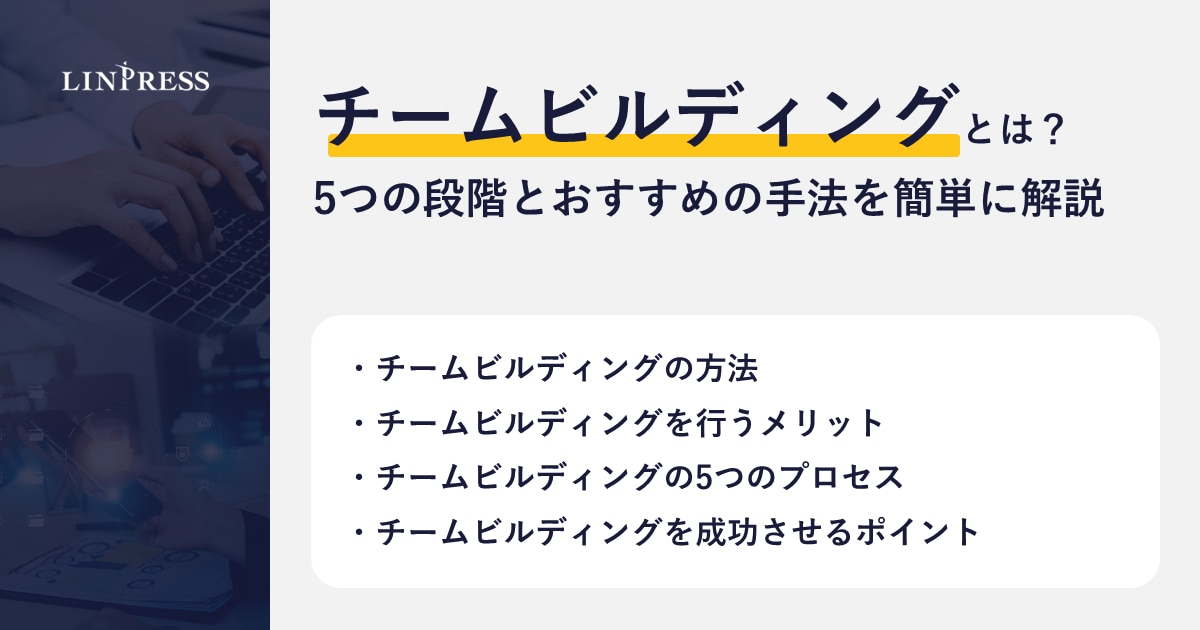
チームビルディングとは?5つの段階とおすすめの手法を簡単に解説
業績に直結する「チームビルディング」は、単なるレクリエーションではなく、組織の土台を強くする重要な施策です。
「チームの成果がなかなか上がらない」「チームメンバー同士の連携がうまくいかない」といったお悩みを持つ企業は、ぜひこの記事で紹介する手順でチームビルディングを実践してみましょう。
本記事では、チームビルディングの基本やその5つの段階(タックマンモデル)、企業内で実践できる手法、外部研修の活用ポイントまでをわかりやすく解説します。
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
チームビルディングとは

チームビルディングとは、メンバー同士の信頼関係を深め、協力し合える関係を築くことを目的とした取り組みです。
単なる人間関係の構築にとどまらず、組織全体として成果を最大化するための土台づくりといえます。具体的には、コミュニケーションの活性化や共通目標の明確化、相互理解の促進などを通じて、チームの一体感を高める活動が行われます。
近年では、リモートワークの普及や人材の多様化により、チーム内の結束力がこれまで以上に重要視されています。業務の効率化や離職防止といった効果も期待できるため、多くの企業で注目されている施策です。
チームビルディングの方法
チームビルディングを効果的に進めるには、目的に応じた方法を選ぶことが重要です。業務の円滑化を狙うのか、関係構築を促したいのかによって手法は異なります。ここでは、職場で実践しやすく、成果にもつながりやすい代表的な方法を5つ紹介します。
ルール作り
ITツール・システムの活用
1on1ミーティングの実施
ゲーム・アクティビティの実施
研修やワークショップの実施
ルール作り
メンバー全員が納得できる「チームのルール」を設けることで、トラブルの予防や責任の明確化が図れます。
たとえば「Slackは24時間以内に返信」「朝会は10分以内に終了」といった具体的なルールがあると、無駄なストレスを軽減し、チーム全体の信頼感を育みやすくなります。
メンバー同士でルールを話し合って決めることも、チームビルディングの一環です。
ITツール・システムの活用
コミュニケーションや業務の可視化をサポートするITツールは、チーム連携を促進する強力な味方です。
たとえば、チャットツールやプロジェクト管理ツールを導入すれば、情報共有の遅延を減らし、メンバー間の認識のズレも防ぎやすくなります。場所や時間に縛られずに連携できる仕組みは、ハイブリッドワーク環境にも適しています。
1on1ミーティングの実施
上司と部下が定期的に1対1で対話する「1on1ミーティング」は、信頼関係の構築や早期の課題発見に役立ちます。
業務報告だけでなく、キャリアやモチベーションに関する話題を取り上げることで、部下の本音を引き出すことができます。安心して話せる場をつくることが、チーム全体の心理的安全性を高める鍵になります。
ゲーム・アクティビティの実施
業務とは離れた場面での「遊び」や「体験」を通じた活動は、チームの壁を取り払うのに効果的です。
アイスブレイクや脱出ゲーム、ワークショップ型のアクティビティなどを取り入れることで、メンバー同士の相互理解が深まり、普段の業務でも協力しやすい関係性が築かれます。楽しみながら信頼を育むことができるのが魅力です。
研修やワークショップの実施
外部講師を招いた研修やワークショップは、短期間で意識を変えるきっかけになります。
専門的な知識や経験をもとに設計されたプログラムは、チームの課題に合わせて柔軟に対応可能です。
また、第三者の視点が入ることで、自分たちでは気づけなかった改善点や強みを発見できることもあります。自社だけでの実施が難しい場合に特に有効な手段です。
社内のつながりを強化する、カスタマイズ性が高い研修サービスをお探しならリンプレスへご相談ください。
ご相談・お問い合わせ
チームビルディングを行うメリット
チームビルディングは単なるレクリエーションではなく、企業の成果に直結する重要な取り組みです。社員一人ひとりの意識改革や組織文化の醸成にもつながり、職場全体の生産性や満足度を大きく高める効果があります。
ここでは、企業担当者が押さえておきたい代表的な4つのメリットを紹介します。
自社のビジョンの浸透
日々の業務に追われる中で、自社のビジョンやミッションが共有されず、形骸化してしまうケースは少なくありません。
チームビルディングを通じてビジョンを再確認する機会を設けることで、全員が同じ方向を向いて業務に取り組む土壌ができます。特に新たな戦略転換期や組織再編のタイミングでは効果的です。
チームメンバーとしてのマインドセット
チームの一員としての自覚を持ち、相手の立場を尊重しながら動けるマインドを育てることは、組織運営の安定に直結します。
個人の成果だけでなく、チーム全体での成功を意識するようになることで、連携力や協調性が向上します。チームビルディングは、この「自分本位からチーム視点へ」という意識の転換を促す有効な手段です。
モチベーションアップ
職場での人間関係やチームの雰囲気は、社員のモチベーションに大きく影響します。
チームビルディングを通じて互いを知り、認め合う関係が築けると、「このチームの一員でいたい」という気持ちが生まれます。また、自分の存在価値を実感できるようになり、仕事への前向きな姿勢が育まれやすくなります。
ベストな人材配置
チームビルディングでは、メンバーの性格や得意分野、価値観を把握する機会が増えるため、人材の適材適所を見極めやすくなります。
誰をどのポジションに配置すべきかが見えてくることで、チーム全体のパフォーマンスも向上します。表面的なスキルだけでなく、相性や思考タイプを踏まえた配置判断が可能になります。
チームビルディング|5つのプロセス
チームが機能するまでには段階的なプロセスがあります。
心理学者タックマンが提唱した、
- 形成期(Forming)
- 混乱期(Storming)
- 統一期(Norming)
- 機能開始期(Performing)
- 散会期(Adjourning)
という5段階のモデル(タックマンモデル)は、チームビルディングにおいて非常に有用です。
ここでは、各段階の特徴と、推奨されるチームビルディング手法を紹介します。
1.形成期(Forming)
形成期は、チームが立ち上がった直後の段階で、メンバー同士がまだ遠慮し合っている状態です。
役割や関係性が定まっておらず、相互の理解も浅いため、信頼関係の構築が重要になります。このフェーズでは、安心して関係性を築ける雰囲気づくりが求められます。
アイスブレイクになる「ゲーム」
初対面の緊張を和らげるには、軽いゲームやレクリエーションが効果的です。
たとえば、自己紹介を兼ねた質問ゲームや、少人数のグループワークを取り入れることで、互いの人柄を知るきっかけになります。楽しみながら距離を縮められるアイスブレイクは、形成期において最も取り入れやすいアプローチのひとつです。
社内でグループワークを行う際のポイントについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
研修でグループワークを行うメリットとは?失敗しないポイントを紹介
2.混乱期(Storming)
混乱期では、メンバーが本音を出し始め、意見の対立や軋轢が表面化します。
この段階は避けられない過程であり、むしろ健全なチーム形成にとって必要なプロセスといえます。重要なのは、この衝突を建設的な議論へと導くことです。
相互理解を促す「イベント」「ワークショップ」
混乱期のフェーズでは、価値観や考え方の違いを理解し合えるような体験型のワークショップが効果的です。
たとえば、ディスカッション形式の研修や役割交換を取り入れたイベントを実施することで、相手の立場や考え方に触れ、共感や尊重の姿勢が育まれます。ファシリテーターによる進行で、衝突の多い混乱期も前向きな成長の機会に変えることが可能です。
3.統一期(Norming)
統一期は、チーム内のルールや役割が明確になり、徐々に安定した関係性が築かれていく段階です。
互いの強みを認め合い、協力して課題に取り組めるようになります。ただし、表面的な安定で終わらせず、深い信頼関係に昇華させることが重要です。
効果を測定する「1on1」
統一期では、メンバー個々の状態や課題を把握しながら、成長をサポートする「1on1ミーティング」が有効です。
定期的に実施することで、業務の成果だけでなく心理的な不安や意見のズレを早期に把握できます。また、個人のモチベーションや関係性の質を見直すきっかけにもなります。
4.機能開始期(Performing)
機能開始期は、チームが最も生産性を発揮し、自律的に動けるようになる段階です。
それぞれが自分の役割を理解し、互いに補完し合いながら目標達成に向けて前進できます。ここではチームの結束力をさらに強化し、成果を最大化することがポイントです。
団結力を強める「アクティビティ」
この時期には、目標に向かって協力するプロジェクト型アクティビティや、リアルな課題解決をテーマにした演習が効果的です。
例えば、グループで成果物を作るワークや、外部フィールドでの共同作業などを通じて、連携力と課題解決力が一段と磨かれます。
5. 散会期(Adjourning)
プロジェクトの終了やチームの解散に向かう最終段階です。達成感と同時に喪失感も生じやすく、次のフェーズに向けての心理的整理が求められます。この時期に適切な締めくくりを行うことで、メンバーの成長と今後の活躍を後押しできます。
チームとしてのフィードバックを行う「振り返り会」
散会期には、成果の振り返りと感謝を伝える「振り返り会」や「クロージングイベント」の実施が有効です。メンバー同士の努力を言葉にして称え合い、達成感を共有することで、経験がポジティブに記憶され、次のチームでも前向きな関わりが期待できます。
研修によるチームビルディングを成功させるポイント
チームビルディングの一環として研修を導入する場合、単にプログラムを実施するだけでは期待した成果を得られないこともあります。
大切なのは、研修をチームの成長につなげるための工夫です。ここでは、研修効果を最大化するために押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。
社員に丸投げしない
研修の成功は、社員に任せきりにせず、経営層や人事担当者が主体的に関与することで高まります。導入前に、チームビルディングが成功した姿や期待する成果を共有し、実施中も様子を把握しながらサポートすることで、参加者の本気度も変わってきます。
「やらされ感」を払拭し、会社全体で取り組む姿勢を示すことが大切です。
方向性やゴールを明確にする
「とりあえず研修を行う」といった曖昧な動機では、参加者の意識が定まりません。
チームビルディング研修の目的や最終的なゴール(例:信頼関係の構築、リーダーシップの強化など)を明確にすることで、参加者の理解度と意欲が高まります。目標に合った内容・進行を選ぶためにも、事前設計が不可欠です。
チームメンバーの自発性を尊重する
研修では、メンバーが自ら気づき、行動を変えるきっかけを得ることが重要です。そのためには、一方的に知識を押し付けるのではなく、話し合いや体験を通じて自発的に考えられる場を用意する必要があります。
自分たちで答えを見出すプロセスが、実際の業務にも活きる“本物の学び”につながります。
チームビルディングのお悩みはリンプレスへ
自社でチームビルディングを進めたいと考えても、「何から始めればいいかわからない」「思ったような成果が出ない」といったお悩みはつきものです。
そんな時は、研修やワークショップを専門とする外部サービスの活用がおすすめです。
リンプレスでは、企業ごとの課題やチームの状況に合わせて、最適な研修プログラムをご提案。実践的で成果につながる内容にこだわり、現場で活きるチーム力の向上をサポートします。初めての導入でも安心してご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。
リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。
まとめ
チームビルディングは、企業の成長や社員の定着に欠かせない取り組みです。タックマンモデルの5段階を意識し、それぞれの段階に適した手法を選ぶことで、チームは着実に成熟していきます。また、外部研修を活用することで、客観的な視点や専門的な知見を取り入れ、より効果的な成果を得ることが可能になります。自社だけでは難しいと感じたときこそ、プロの力を借りるタイミングです。組織の未来を見据えたチームづくりに、ぜひ一歩踏み出してみてください。
リンプレスは、カスタマイズ可能な実務に直結する体験型研修プログラムを通じて、社内のチーム力を強化します。ぜひお気軽にご相談ください。
<文/文園 香織>